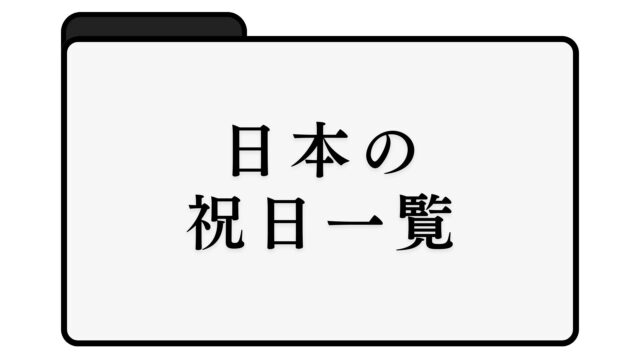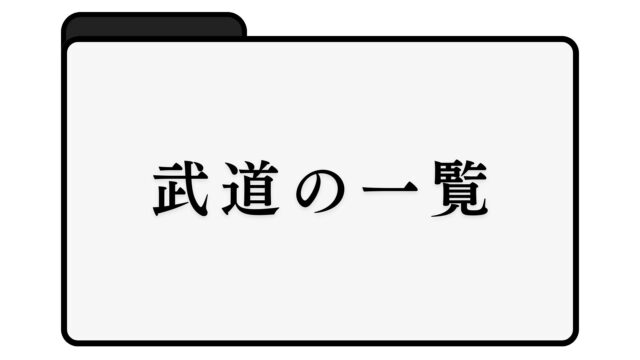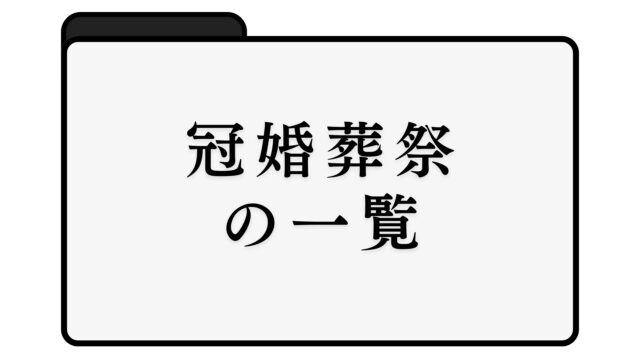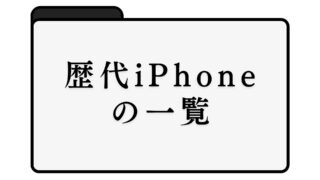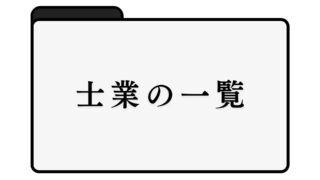今回は、日本国内で行われている年間行事をまとめてみました。
日本の行事は非常に多岐にわたり、全国共通のものから地域色の濃いもの、伝統的なものから現代的なものまで様々です。
ここでは一般的に広く認知され、多くの人々が意識する主要な年間行事を月ごとにまとめてご紹介します。
1月 (睦月 – むつき)
元日 (がんじつ) / 正月 (しょうがつ)
概要: 新しい年の始まりを祝う、日本で最も重要な行事の一つ。多くの企業や学校が休みとなる「正月休み」があります。
主な過ごし方: 初詣 (神社仏閣へ新年の参拝)、おせち料理を食べる、お雑煮を食べる、年賀状の確認、お年玉を渡す・もらう、凧揚げ、羽根つき、かるた、福袋の購入など。
国民の祝日: 1月1日 (元日)
仕事始め (しごとはじめ)
概要: 官公庁や多くの企業で、年末年始の休暇が明けて業務を開始する日。
七草の節句 (ななくさのせっく) / 人日 (じんじつ) の節句
概要: 1月7日に、春の七草を入れた「七草がゆ」を食べ、無病息災や長寿を願う行事。
鏡開き (かがみびらき)
概要: 正月に神仏に供えた鏡餅を下げて食べる行事。一般的に1月11日に行われます。刃物を使わず木槌などで割るのが習わしです。
成人の日 (せいじんのひ)
概要: 年度内に20歳 (※2022年4月1日より18歳) になる若者を祝い励ます日。各地で成人式が開催されます。
国民の祝日: 1月の第2月曜日
小正月 (こしょうがつ)
概要: 1月15日を中心とした期間。豊作祈願や、どんど焼き (左義長) などが行われる地域もあります。
2月 (如月 – きさらぎ)
節分 (せつぶん)
概要: 立春の前日で、季節の分かれ目。豆まきをして鬼 (邪気) を払い、福を呼び込む行事。「恵方巻」を食べる習慣も広まっています。
バレンタインデー
概要: 2月14日。主に女性から男性へチョコレートを贈って愛情や感謝の気持ちを伝える日として定着しています。
建国記念の日 (けんこくきねんのひ)
概要: 日本の建国を祝う日。
国民の祝日: 2月11日
天皇誕生日 (てんのうたんじょうび)
概要: 今上天皇の誕生日を祝う日。
国民の祝日: 2月23日 (2020年より)
針供養 (はりくよう)
概要: 折れたり使えなくなったりした針を豆腐やこんにゃくなどに刺して供養し、裁縫の上達を願う行事。主に2月8日や12月8日に行われます。
3月 (弥生 – やよい)
ひな祭り (桃の節句 – もものせっく) / 上巳 (じょうし) の節句
概要: 3月3日。女の子の健やかな成長と幸せを願う行事。雛人形を飾り、ちらし寿司、ハマグリのお吸い物、ひなあられ、菱餅などを食べます。
ホワイトデー
概要: 3月14日。バレンタインデーに贈り物をもらった男性が、お返しをする日として広まっています。
お彼岸 (おひがん) (春)
概要: 春分の日を中日とした前後3日間、計7日間。先祖の墓参りをし、供養を行います。ぼたもち (おはぎ) を食べる習慣があります。
春分の日 (しゅんぶんのひ)
概要: 昼と夜の長さがほぼ同じになる日。「自然をたたえ、生物をいつくしむ」日とされています。
国民の祝日: 3月20日または21日頃
卒業式 (そつぎょうしき)
概要: 学校の卒業を祝う式典。3月は多くの学校で卒業シーズンです。
4月 (卯月 – うづき)
エイプリルフール
概要: 4月1日。嘘をついても良いとされる日。ただし、他人を傷つけないユーモラスな嘘に限られます。
お花見 (おはなみ)
概要: 桜の花を観賞する行事。公園などで宴会を開くこともあります。桜の開花時期は地域によって異なりますが、3月下旬から4月上旬がピークとなる地域が多いです。
入学式 (にゅうがくしき)・入社式 (にゅうしゃしき)
概要: 新しい学年や社会人としての生活が始まる式典。4月は新年度の始まりです。
灌仏会 (かんぶつえ) / 花まつり (はなまつり)
概要: 4月8日。お釈迦様の誕生を祝う仏教行事。甘茶を誕生仏にかける風習があります。
昭和の日 (しょうわのひ)
概要: 昭和天皇の誕生日。「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす」日。
国民の祝日: 4月29日
5月 (皐月 – さつき)
ゴールデンウィーク (GW)
概要: 4月末から5月初めにかけての祝日が多い期間。長期休暇となり、旅行やレジャーに出かける人が増えます。(昭和の日、憲法記念日、みどりの日、こどもの日が含まれます)
憲法記念日 (けんぽうきねんび)
概要: 日本国憲法の施行を記念する日。
国民の祝日: 5月3日
みどりの日 (みどりのひ)
概要: 「自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ」日。
国民の祝日: 5月4日
こどもの日 (端午の節句 – たんごのせっく)
概要: 5月5日。「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」日。男の子の健やかな成長を祝い、鯉のぼりや五月人形 (鎧兜) を飾り、柏餅やちまきを食べます。
国民の祝日: 5月5日
母の日 (ははのひ)
概要: 5月の第2日曜日。母親に感謝の気持ちを伝える日。カーネーションを贈るのが一般的です。
6月 (水無月 – みなづき)
衣替え (ころもがえ)
概要: 季節に合わせて衣服を替えること。一般的に6月1日と10月1日に行われます。
父の日 (ちちのひ)
概要: 6月の第3日曜日。父親に感謝の気持ちを伝える日。
梅雨入り (つゆいり)
概要: 本格的な雨季の始まり。地域によって時期は異なりますが、沖縄・奄美地方を除くと、多くの地域で6月頃に梅雨入りします。
夏越の祓 (なごしのはらえ)
概要: 6月30日に行われる神事。半年の間にたまった穢れを祓い、残り半年の無病息災を祈願します。茅の輪くぐりなどが行われます。
7月 (文月 – ふみづき)
海の日 (うみのひ)
概要: 「海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う」日。
国民の祝日: 7月の第3月曜日
七夕 (たなばた) / 星祭 (ほしまつり)
概要: 7月7日 (地域によっては月遅れの8月7日)。織姫と彦星が年に一度会えるという伝説に基づき、短冊に願い事を書いて笹竹に飾ります。
お中元 (おちゅうげん)
概要: 日頃お世話になっている人に感謝の気持ちを込めて品物を贈る習慣。主に7月初旬から中旬にかけて贈られます。
土用の丑の日 (どようのうしのひ)
概要: 夏の土用の期間にある丑の日。うなぎを食べて夏バテを防ぐという習慣があります。
夏祭り (なつまつり)・花火大会 (はなびたいかい)
概要: 7月から8月にかけて、全国各地で様々な夏祭りや花火大会が開催されます。盆踊り、屋台、神輿などが楽しめます。
海開き・山開き (うみびらき・やまびらき)
概要: 海水浴場や登山のシーズンが始まることを意味します。安全祈願の神事が行われることもあります。
8月 (葉月 – はづき)
お盆 (おぼん)
概要: 先祖の霊を迎えて供養する期間。一般的に8月13日から16日頃 (地域によって7月の場合も)。迎え火や送り火を焚いたり、盆踊りが行われたりします。多くの企業が「お盆休み」となります。
山の日 (やまのひ)
概要: 「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」日。
国民の祝日: 8月11日
終戦記念日 (しゅうせんきねんび) / 全国戦没者追悼式
概要: 8月15日。第二次世界大戦の終結を記念し、戦没者を追悼し平和を祈念する日。
夏の高校野球 (全国高等学校野球選手権大会)
概要: 毎年8月に甲子園球場で開催される高校野球の全国大会。国民的な関心事の一つです。
9月 (長月 – ながつき)
防災の日 (ぼうさいのひ)
概要: 9月1日。関東大震災が発生した日にちなみ、災害への備えを啓発する日。各地で防災訓練が行われます。
敬老の日 (けいろうのひ)
概要: 「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う」日。
国民の祝日: 9月の第3月曜日
お彼岸 (おひがん) (秋)
概要: 秋分の日を中日とした前後3日間、計7日間。春と同様に先祖の墓参りをし、供養を行います。おはぎ (ぼたもち) を食べる習慣があります。
秋分の日 (しゅうぶんのひ)
概要: 昼と夜の長さがほぼ同じになる日。「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ」日とされています。
国民の祝日: 9月22日または23日頃
お月見 (おつきみ) / 十五夜 (じゅうごや) / 中秋の名月 (ちゅうしゅうのめいげつ)
概要: 旧暦8月15日の夜に月を観賞する行事。ススキを飾り、月見団子や里芋などを供えます。
10月 (神無月 – かんなづき)
衣替え (ころもがえ)
概要: 10月1日。夏服から冬服へ替えます。
スポーツの日 (すぽーつのひ)
概要: 「スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう」日。以前は「体育の日」でした。
国民の祝日: 10月の第2月曜日
十三夜 (じゅうさんや)
概要: 旧暦9月13日の夜の月。十五夜の月見とあわせて行うのが良いとされています。「栗名月」「豆名月」とも呼ばれます。
ハロウィン
概要: 10月31日。元々は古代ケルト人の収穫祭が起源。日本では仮装パーティーやイベントとして楽しまれています。
読書の秋・食欲の秋・芸術の秋・スポーツの秋
概要: 気候が良く、様々な活動に適した季節とされることから、こうした言葉で表現されます。文化祭や運動会などが多く開催されます。
紅葉狩り (もみじがり)
概要: 紅葉した木々を観賞すること。10月頃から始まり、地域や標高によって見頃の時期が異なります。
11月 (霜月 – しもつき)
文化の日 (ぶんかのひ)
概要: 「自由と平和を愛し、文化をすすめる」日。文化勲章の授与式が行われたり、文化的なイベントが開催されたりします。
国民の祝日: 11月3日
七五三 (しちごさん)
概要: 11月15日を中心に、男の子は3歳と5歳 (または5歳のみ)、女の子は3歳と7歳の年に、子供の健やかな成長を祝って神社仏閣に参拝する行事。千歳飴を持ちます。
酉の市 (とりのいち)
概要: 11月の酉の日に関東地方の神社を中心に行われる祭り。開運招福や商売繁盛を願って縁起物の熊手などが売られます。
勤労感謝の日 (きんろうかんしゃのひ)
概要: 「勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう」日。
国民の祝日: 11月23日
ボジョレー・ヌーヴォー解禁
概要: フランスのボジョレー地区でその年に収穫されたブドウで造られる新酒ワインの販売が解禁される日。11月の第3木曜日。
12月 (師走 – しわす)
お歳暮 (おせいぼ)
概要: 年末に、日頃お世話になっている人に感謝の気持ちを込めて品物を贈る習慣。一般的に12月初旬から20日頃までに贈られます。
事始め (ことはじめ)
概要: 正月の準備を始める日。地域によって異なり、一般的に12月8日や13日に行われます。
冬至 (とうじ)
概要: 1年で最も昼が短く、夜が長い日。かぼちゃを食べたり、ゆず湯に入ったりする習慣があります。(12月21日または22日頃)
クリスマス
概要: 12月25日。イエス・キリストの降誕を祝う日。日本では宗教的な意味合いよりも、家族や恋人と過ごすイベントとして定着しています。クリスマスケーキを食べたり、プレゼントを交換したりします。
大掃除 (おおそうじ)
概要: 年末に家全体をきれいに掃除し、新年を迎える準備をすること。
仕事納め (しごとおさめ)
概要: 官公庁や多くの企業で、その年の業務を終える日。
大晦日 (おおみそか)
概要: 1年の最後の日。年越しそばを食べたり、除夜の鐘を聞いたりして新年を迎えます。NHK紅白歌合戦も大晦日の風物詩です。
まとめ
上記以外にも、各地域には独自の伝統的な祭りや行事が数多く存在します (例: 京都の祇園祭、青森のねぶた祭、徳島の阿波おどりなど)。
この一覧が、日本の豊かな文化や季節の移り変わりを感じるための一助となれば幸いです!