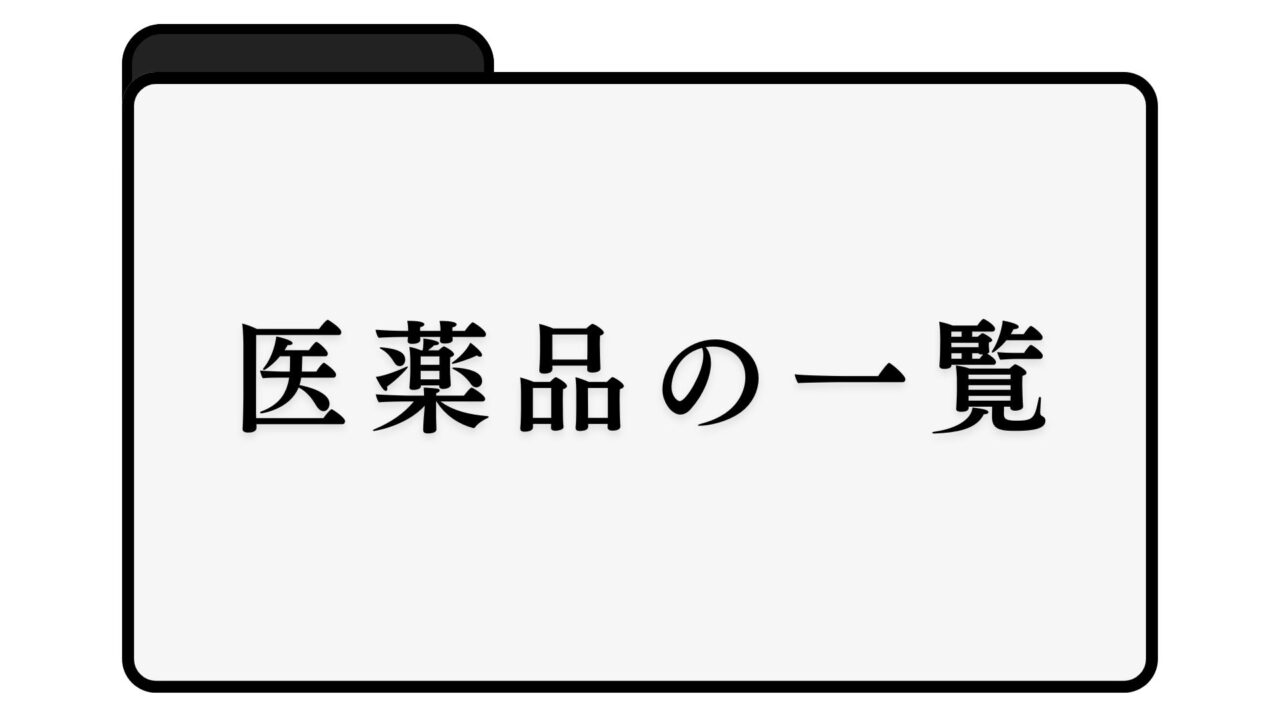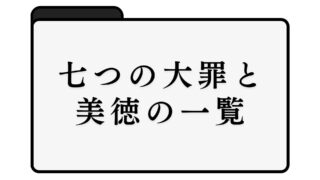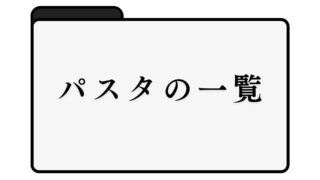今回は、薬の種類と分類などについてまとめてみました。
薬は、その効果やリスク、入手方法などによって、法律(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、通称:医薬品医療機器等法)に基づいて厳密に分類されています。
これは、薬を安全かつ効果的に使用するために非常に重要です。
1. 医療用医薬品(処方薬)
医療用医薬品は、医師・歯科医師の診断に基づき、その処方箋または指示によって使用される医薬品です。
病気の治療や診断を主な目的としているため市販薬に比べて効果が高いものが多く、その反面、副作用のリスクも高いため、専門家による適切な管理のもとで使用される必要があります。
特徴:
高い効果: 特定の病気や症状に対して、強い効果を発揮するように設計されています。
専門的な知識が必要: 薬の選択、用法・用量の決定、副作用のモニタリングなど、医師や薬剤師の専門的な判断が必要です。
個別対応: 患者さん一人ひとりの症状、体質、年齢、他の服用薬などを考慮して処方されます。
入手方法:
医療機関を受診し、医師・歯科医師から処方箋を発行してもらい、薬局で薬剤師に調剤してもらうことで入手できます。
表示:
通常、個別の薬の箱や説明書に「処方箋医薬品」などの表示がありますが、患者さんが直接目にすることは少ないかもしれません。薬袋や薬剤情報提供書で薬剤師から説明を受けます。
例:
抗生物質: アモキシシリン、クラリスロマイシンなど(細菌感染症治療)
降圧薬: アムロジピン、オルメサルタンなど(高血圧治療)
血糖降下薬: メトホルミン、インスリン製剤など(糖尿病治療)
抗がん剤: 様々な種類があります(がん治療)
精神神経用薬: SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)、ベンゾジアゼピン系睡眠薬など(うつ病、不安障害、不眠症治療)
その他、非常に多くの種類があります。
使用上の注意点:
必ず医師や薬剤師の指示通りに服用してください。
自己判断で服用量を変えたり、中止したりしないでください。
副作用と思われる症状が出た場合は、すぐに医師や薬剤師に相談してください。
他の人に譲渡したり、勧めたりしないでください。
2. 一般用医薬品(OTC医薬品、市販薬)
一般用医薬品は、自分の判断で購入し軽度な身体の不調の初期治療やセルフケアに使用される医薬品です。
リスクの程度に応じて「要指導医薬品」と「第1類~第3類医薬品」に分類されます。
2-1. 要指導医薬品
要指導医薬品は、医療用医薬品から一般用医薬品に移行して間もない医薬品(スイッチOTC医薬品)や、劇薬に指定されている一般用医薬品などです。
副作用のリスクが比較的高く、適正な使用のために薬剤師による対面での情報提供と指導が義務付けられています。
特徴:
スイッチOTC: これまで医療用として使われていた有効成分が、市販薬として使えるようになったもの。
劇薬: 毒薬に次いで生体に対する作用が強く、使い方を誤ると危険性が高いもの。
安全な使用のため、十分な情報提供と理解が必要です。
販売方法:
薬剤師が常駐する薬局・薬店でのみ購入可能です。
購入時には、薬剤師から対面で書面を用いた情報提供・指導を受けることが義務付けられています。
インターネットや電話での販売はできません。
表示:
パッケージに「要指導医薬品」と明確に表示されています。
例:
一部の禁煙補助薬(ニコチンを含まないバレニクリン酒石酸塩など ※商品が限定的)
一部のアレルギー性鼻炎治療薬(医療用成分がスイッチされたばかりのもの)
※具体的な商品名は変更されることがあるため、購入時に確認が必要です。
購入時のポイント:
必ず薬剤師の説明をよく聞き、理解した上で使用してください。
使用上の注意や副作用について、疑問があれば遠慮なく質問しましょう。
2-2. 第1類医薬品
第1類医薬品は、一般用医薬品の中で、副作用などにより日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生じるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要なもの。
特徴:
効果が高い反面、副作用のリスクも相対的に高いとされています。
適切な情報提供なしに使用すると、健康被害を生じる可能性があります。
販売方法:
薬剤師が常駐する薬局・薬店でのみ購入可能です。
購入時には、薬剤師から書面を用いた情報提供を受けることが義務付けられています(質問がなくても説明が必要です)。
インターネット販売も可能ですが、薬剤師による情報提供(メール等)が義務付けられています。
表示:
パッケージに「第1類医薬品」と明確に表示されています。
例:
H2ブロッカー含有胃腸薬: ガスター10(ファモチジン)、アシノンZ(ニザチジン)など(胃酸分泌を抑える)
一部の解熱鎮痛薬: ロキソニンS(ロキソプロフェンナトリウム水和物)など
一部の発毛剤: リアップ(ミノキシジル)など
一部のアレルギー専用鼻炎薬: アレグラFX(フェキソフェナジン塩酸塩)、クラリチンEX(ロラタジン)など
ヘルペス再発治療薬: アクチビア軟膏、アラセナS(アシクロビル、ビダラビン)など
購入時のポイント:
薬剤師の説明をよく聞き、用法・用量、副作用、使用してはいけない人などをしっかり理解してください。
他の薬を服用している場合や、持病がある場合は必ず薬剤師に伝えましょう。
2-3. 第2類医薬品
第2類医薬品は、一般用医薬品の中で、副作用などにより日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生じるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)。
まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含みます。
特徴:
市販薬の中で最も品目数が多く、風邪薬や解熱鎮痛薬など、日常的に使用される多くの薬が該当します。
薬剤師または登録販売者からの情報提供は努力義務とされています(購入者から相談があれば説明する義務があります)。
販売方法:
薬剤師または登録販売者がいる薬局・薬店で購入可能です。
インターネット販売も可能です。
表示:
パッケージに「第2類医薬品」と明確に表示されています。
例:
多くの風邪薬(総合感冒薬): パブロン、ルル、エスタックなど
多くの解熱鎮痛薬: バファリンA(アスピリン)、イブ(イブプロフェン)、セデス(アセトアミノフェン、エテンザミドなど)など
多くの漢方薬・生薬製剤
多くの胃腸薬: 大田胃散、キャベジンコーワαなど
多くの目薬、点鼻薬
多くの外皮用薬(塗り薬、湿布など)
購入時のポイント:
薬剤師や登録販売者に相談し、自分の症状や体質に合ったものを選びましょう。
使用前に添付文書をよく読み、用法・用量を守りましょう。
「してはいけないこと」「相談すること」の項目を特に注意して確認してください。
2-3-1. 指定第2類医薬品
指定第2類医薬品は、第2類医薬品の中でも、特に注意を要する成分を含んでいるものです。
副作用のリスクが他の第2類医薬品よりも相対的に高く、小児や高齢者、妊婦などが使用する場合や、長期間の使用、他の薬との飲み合わせなどに特に注意が必要です。
特徴:
依存性がある成分や、相互作用に注意が必要な成分が含まれている場合があります。
専門家からの積極的な情報提供が推奨されます。
販売方法:
第2類医薬品と同様です。
表示:
パッケージに「第②類医薬品」または「第2類医薬品」と表示され、数字の「2」が四角または丸で囲まれています。
例:
一部の解熱鎮痛薬: イブプロフェン、アスピリン(アセチルサリチル酸)、エテンザミドなどを含むもの
一部の風邪薬: プソイドエフェドリン塩酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、メチルエフェドリン塩酸塩などを含むもの
一部の鎮咳去痰薬: コデインリン酸塩水和物、デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物などを含むもの
一部の睡眠改善薬: ジフェンヒドラミン塩酸塩など
一部の便秘薬: センノシド、ビサコジルなど(刺激性下剤)
一部の痔の薬(ステロイド含有など)
購入時のポイント:
薬剤師または登録販売者に積極的に相談し、使用上の注意点(特に使用期間、併用薬、副作用)について詳しい説明を受けましょう。
添付文書を特に熟読し、理解した上で使用してください。
漫然と長期間使用しないようにしましょう。
2-4. 第3類医薬品
第3類医薬品は、第1類医薬品および第2類医薬品以外の一般用医薬品。
副作用のリスクが比較的低く、日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがあるものです。
特徴:
比較的安全性が高いとされています。
薬剤師や登録販売者からの情報提供の法的義務はありませんが、購入者から相談があれば応じる義務があります。
販売方法:
薬剤師または登録販売者がいる薬局・薬店で購入可能です。
インターネット販売も可能です。
表示:
パッケージに「第3類医薬品」と明確に表示されています。
例:
ビタミン剤: ビタミンC主薬製剤、ビタミンB群製剤など
整腸剤: ビオフェルミンS錠(乳酸菌製剤)、ザ・ガードコーワ整腸錠(納豆菌・乳酸菌・健胃生薬)など
一部の消化薬: 新タカヂア錠(消化酵素剤)など
一部の湿布薬・塗り薬: サロンパス(サリチル酸メチルなど)、メンソレータム軟膏(カンフル、メントールなど)
消毒薬: マキロンs(ベンゼトニウム塩化物など)
うがい薬: イソジンうがい薬(ポビドンヨード)など
購入時のポイント:
リスクが低いとはいえ医薬品ですので、使用前に添付文書を読み、用法・用量を守りましょう。
効果が感じられない場合や、長期間使用する場合は医師や薬剤師に相談しましょう。
3. 医薬部外品
医薬部外品は、医薬品と化粧品の中間に位置づけられるもので、人体に対する作用が緩和なものです。
主な目的は以下の通りです。
吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
あせも、ただれ等の防止
脱毛の予防、育毛又は除毛
人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除
病気の治療や予防を直接的な目的とはしていません。
医薬品との違い:
「治療」ではなく、「防止・衛生」が主な目的です。
効果・効能の表現が医薬品よりも限定的で、穏やかです(例:「ニキビを防ぐ」「メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ」など)。
副作用のリスクは医薬品に比べて低いとされています。
販売方法:
薬局やドラッグストアのほか、コンビニエンスストアやスーパーなどでも販売されています。
薬剤師や登録販売者の配置義務はありません。
表示:
商品に「医薬部外品」と表示されています。「薬用」と表示されているものも多くあります(例:薬用歯磨き、薬用石鹸、薬用化粧品)。
例:
薬用歯磨き粉: フッ素配合、歯周病予防成分配合など
薬用石鹸・薬用ハンドソープ: 殺菌成分配合など
薬用化粧品: 美白化粧品(ビタミンC誘導体、トラネキサム酸配合など)、ニキビ予防化粧品(サリチル酸、グリチルリチン酸配合など)
制汗剤・デオドラント剤
育毛剤・養毛剤
染毛剤(一部)
殺虫剤(人体に直接使用するもの): 蚊よけスプレー、虫刺され薬(かゆみ止めなどではなく、忌避剤)
ビタミン含有保健薬(栄養ドリンクの一部): リポビタンDなど(指定医薬部外品)
浴用剤(入浴剤): 温浴効果を高めるもの、荒れ性・しっしんなどに効果があるもの
コンタクトレンズ装着液
口中清涼剤、のど飴(一部)
選ぶ際のポイント:
「薬用=医薬品」ではないことを理解しましょう。
「防止」「衛生」といった目的で使用し、治療効果を過度に期待しないようにしましょう。
肌に使用するものは、自分の肌質に合うか確認しましょう。
4. 化粧品
化粧品は、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚もしくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものです。
医薬品や医薬部外品のような「有効成分」による積極的な効果・効能はうたえません。
医薬部外品との違い:
化粧品は「有効成分」を含まず、薬理作用を期待するものではありません。
医薬部外品は特定の効果(例:美白、ニキビ予防)をうたえますが、化粧品は「肌を整える」「うるおいを与える」といった化粧品としての効能範囲に限定されます。
販売方法:
薬局、ドラッグストア、百貨店、コンビニ、雑貨店など、幅広い場所で販売されています。
販売に関する専門家の配置義務はありません。
表示:
商品に「化粧品」と表示されることは少ないですが、医薬品や医薬部外品のような表示はありません。成分表示は義務付けられています。
例:
スキンケア製品: 化粧水、乳液、美容液、クリーム、洗顔料、クレンジングなど
メイクアップ製品: ファンデーション、口紅、アイシャドウ、マスカラなど
ヘアケア製品: シャンプー、コンディショナー、トリートメント、ヘアスタイリング剤など
ボディケア製品: ボディソープ、ボディローション、ハンドクリームなど
香水
選ぶ際のポイント:
自分の肌質や髪質、目的に合ったものを選びましょう。
アレルギー体質の方は、成分表示を確認し、パッチテストなどを行うと良いでしょう。
医薬品のような治療効果を期待しないようにしましょう。
まとめ
これら薬の分類を正しく理解し、それぞれの薬や製品の特性を知ることで、より安全で適切なセルフケアや治療選択が可能になります。
不明な点があれば、必ず医師、薬剤師、登録販売者などの専門家に相談するようにしてください。
それでは健康に気を付けて明日も頑張りましょう!