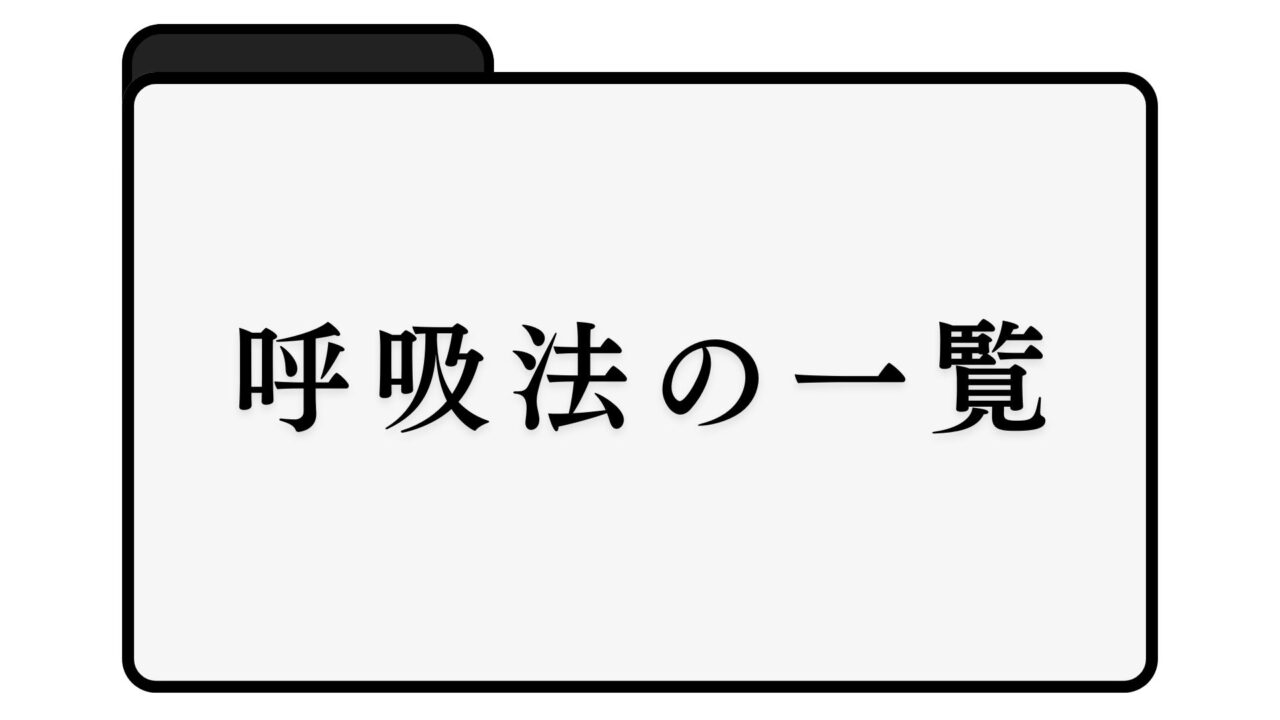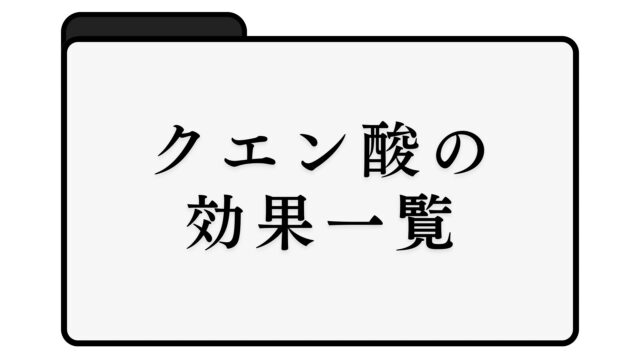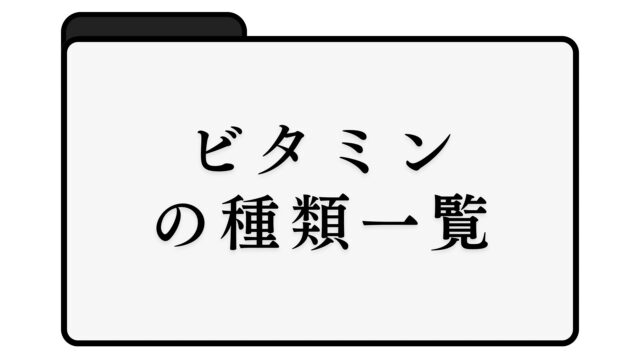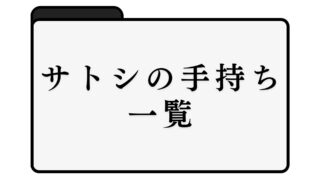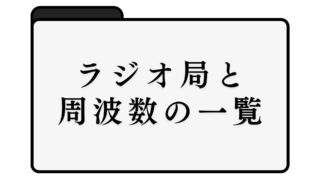今回は、古今東西様々なシーンで活用されている呼吸法についてまとめてみました。
呼吸法は、その目的や効果によって様々な種類があり、カテゴリー分けも多岐にわたります。ここでは、代表的なカテゴリーと、それぞれの用途・効果、基本的なやり方について詳しくご紹介します。
無理のない範囲で行い、めまいや不快感を感じたらすぐに中止してください。
一部の専門的な呼吸法は、指導者の下で行うことが推奨されます。
カテゴリー1:リラックス・ストレス軽減を目的とした呼吸法
主に副交感神経を優位にし、心身を落ち着かせることを目指します。
1. 腹式呼吸(ふくしきこきゅう)
用途・効果:
リラックス効果、ストレス軽減
自律神経のバランスを整える
血圧の安定、心拍数の低下
睡眠の質の向上
不安感の軽減
やり方:
楽な姿勢(仰向け、座位など)をとります。
片手をお腹に、もう一方の手を胸に置きます(お腹の動きを確認するため)。
鼻からゆっくりと息を吸い込みます。この時、胸ではなくお腹が膨らむのを感じます(お腹に置いた手が持ち上がる)。
口をすぼめて、吸った時間の倍くらいの時間をかけてゆっくりと息を吐き出します。お腹がへこんでいくのを感じます。
これを数分間繰り返します。
2. 4-7-8呼吸法(よん なな はち こきゅうほう)
用途・効果:
深いリラックス効果、入眠促進
不安や緊張の緩和
パニックの鎮静
やり方:
楽な姿勢をとります。舌先を上の前歯の裏側の歯茎につけます。
口から「ふーっ」と完全に息を吐き切ります。
口を閉じ、鼻から4秒かけて静かに息を吸い込みます。
7秒間息を止めます。
口から「ふーっ」と音を立てながら8秒かけて完全に息を吐き切ります。
これを1サイクルとし、4サイクル繰り返します。慣れるまでは回数を減らしても構いません。
3. ボックスブリージング(箱型呼吸法)
用途・効果:
ストレス管理、冷静さの維持
集中力の向上
感情のコントロール
やり方:
楽な姿勢をとります。
鼻から4秒かけて息を吸い込みます。
4秒間息を止めます。
口または鼻から4秒かけて息を吐き出します。
4秒間息を止めます(息を吐ききった状態で)。
これを数分間繰り返します。秒数は自分に合わせて3~5秒程度で調整可能です。
4. 漸進的筋弛緩法(ぜんしんてききんしかんほう)に伴う呼吸
用途・効果:
身体の緊張緩和、リラックス
不眠改善
不安軽減
やり方:
楽な姿勢をとります。
体の各部位(手、腕、肩、首、顔、背中、腹部、足など)に順番に力を入れ(5~10秒)、その後一気に力を抜きます(15~20秒)。
力を入れる際に息を吸い、力を抜く際にゆっくりと息を吐き出すように呼吸を合わせます。
全身の筋肉を順番に行います。
カテゴリー2:集中力向上・覚醒を目的とした呼吸法
主に交感神経を適度に刺激し、心身をクリアにすることを目指します。
1. 胸式呼吸(きょうしきこきゅう)
用途・効果:
交感神経をやや優位にし、心身を活動的にする
集中力の向上
運動前のウォーミングアップ
ピラティスなどで体幹を意識する際に用いられる
やり方:
楽な姿勢をとります。
鼻から息を吸い込み、胸(肋骨)を広げるように意識します。お腹はあまり膨らませません。
口または鼻から息を吐き出し、胸を閉じるように意識します。
腹式呼吸より浅く速い呼吸になりやすいですが、意識的にゆっくり行うことも可能です。
2. 片鼻呼吸(かたはなこきゅう / ナディショーダナ)
用途・効果:
自律神経のバランス調整(左右の鼻孔はそれぞれ異なる神経系と関連するとされる)
集中力向上、精神の安定
心身の浄化、リフレッシュ
(リラックス効果もあるため、カテゴリー1と重複する側面あり)
やり方:
楽な座位をとります。
右手の人差し指と中指を眉間に置くか、折り曲げます。親指で右の鼻孔を、薬指で左の鼻孔を操作します。
まず、両方の鼻孔からゆっくりと息を吐き切ります。
親指で右鼻孔を軽く閉じ、左鼻孔からゆっくりと4秒かけて息を吸い込みます。
薬指で左鼻孔を閉じ(両鼻孔を閉じた状態)、4~8秒程度息を止めます(クンバカ)。無理のない範囲で。
親指を離し、右鼻孔からゆっくりと8秒かけて息を吐き出します。
そのまま右鼻孔からゆっくりと4秒かけて息を吸い込みます。
親指で右鼻孔を閉じ、4~8秒程度息を止めます。
薬指を離し、左鼻孔からゆっくりと8秒かけて息を吐き出します。
これで1サイクルです。数サイクル繰り返します。
注意: 息止め(クンバカ)は慣れてから、または指導者の下で行うのが安全です。最初は息止めなしでも構いません。
3. カパラバティ(火の呼吸 / 浄化の呼吸法) ※ヨガの技法、注意が必要
用途・効果:
頭脳明晰、集中力向上
身体の浄化、デトックス
活力向上、眠気覚まし
腹筋の強化
やり方:
楽な座位をとります。背筋を伸ばします。
自然に息を吸い込みます。
お腹を強くへこませる力を使って、鼻から「フッ!フッ!」と短く強く息を吐き出します。
息を吸うのは自然に任せ、吐く息に意識を集中します。
これを1秒間に1~2回程度のペースで、10~30回程度繰り返します。
終わったら自然な呼吸に戻り、数回深呼吸します。
注意: 高血圧、心臓疾患、妊娠中、めまいを起こしやすい方などは行わないでください。初めて行う場合は、必ず専門家の指導を受けてください。
カテゴリー3:健康増進・身体機能向上を目的とした呼吸法
1. 完全呼吸(かんぜんこきゅう / ヨガのディールガ・プラナヤマ)
用途・効果:
肺活量の増大、最大限の酸素摂取
全身への酸素供給促進、疲労回復
リラックス効果、精神安定
内臓機能の活性化
やり方:
楽な姿勢(仰向けが分かりやすい)をとります。
まず、完全に息を吐き切ります。
息を吸い始め、まずお腹を膨らませます(腹式)。
次いで、胸(肋骨)を広げるように息を吸い込みます(胸式)。
最後に、鎖骨のあたりまで息を満たすように、肩をわずかに持ち上げる感じで吸い込みます。
息を吐くときは、鎖骨部→胸部→腹部の順に、ゆっくりと完全に息を吐き切ります。
これを滑らかに連続して行います。
2. 逆腹式呼吸(ぎゃくふくしきこきゅう)
用途・効果:
体幹(インナーマッスル)の強化
内臓のマッサージ効果
気の流れを整える(気功や武道で用いられる)
集中力向上
やり方:
楽な姿勢をとります。
鼻からゆっくりと息を吸い込みながら、お腹をへこませていきます(横隔膜が上がり、腹圧が高まる)。
口または鼻からゆっくりと息を吐き出しながら、お腹を自然に膨らませていきます。
通常の腹式呼吸とはお腹の動きが逆になります。最初は難しく感じるかもしれません。
3. 丹田呼吸法(たんでんこきゅうほう)
用途・効果:
精神安定、気の充実
集中力・決断力の向上
冷え性の改善
武道や瞑想、芸事の基礎
やり方:
楽な座位(あぐらや正座など)をとり、背筋を軽く伸ばします。
意識をおへその下数センチの奥にある「丹田(たんでん)」に集中します。
鼻からゆっくりと息を吸い込み、丹田に気が満ちていくようなイメージをします(腹式呼吸でお腹が膨らむ)。
口または鼻からゆっくりと長く息を吐き出し、丹田から全身に気が巡るようなイメージをします(お腹がへこむ)。
呼吸の長さや深さよりも、丹田への意識とゆったりとしたリズムを大切にします。
カテゴリー4:特定の状況下での呼吸法
1. スポーツ時の呼吸法
用途・効果:
パフォーマンス向上、持久力維持
集中力維持、力の発揮
疲労軽減
やり方:
種目や状況により異なりますが、基本は「吸う・吐く」のリズムを動作に合わせることです。
例(ランニング): 2歩で吸って2歩で吐く、3歩で吸って3歩で吐くなど、自分に合ったリズムを見つける。苦しくなったら深く吐くことを意識する。
例(ウェイトトレーニング): 力を入れる瞬間に息を吐き、力を抜く(戻す)時に息を吸う。息を止めすぎないように注意。
共通: 運動前後に深呼吸を取り入れ、心身を整える。
2. 発声のための呼吸法(主に腹式呼吸の応用)
用途・効果:
安定した声量、響きのある声
長時間の発生における疲労軽減
声のコントロール向上
やり方:
腹式呼吸を基本とし、息を吸う際にお腹と脇腹、背中側も膨らむようなイメージで深く吸い込みます(横隔膜をしっかり下げる)。
吐く息を一定の圧力でコントロールしながら、声を乗せていきます。お腹で息を支える感覚が重要です。
「スー」「シー」などの摩擦音で長く息を吐く練習や、母音でのロングトーン練習が効果的です。
3. 睡眠導入のための呼吸法
用途・効果:
心身のリラックス、入眠促進
やり方:
カテゴリー1で紹介した「腹式呼吸」や「4-7-8呼吸法」が特に有効です。
ポイントは、吸う息よりも吐く息を長く、ゆっくりと行うことです。
呼吸に意識を集中することで、余計な考え事から離れる効果も期待できます。
4. パニック時・不安時の呼吸法
用途・効果:
過呼吸の予防・緩和
冷静さを取り戻す
やり方:
ゆっくりとした腹式呼吸: 最も基本的で安全な方法です。吸う息よりも吐く息を長く、ゆっくりと行い、呼吸のリズムを整えます。
呼吸のカウント: 「1、2、3、4で吸って、1、2、3、4、5、6で吐く」など、数を数えながら行うと意識を呼吸に集中しやすくなります。
注意: かつて推奨された紙袋法(ペーパーバッグ法)は、二酸化炭素濃度が上がりすぎるリスクがあるため、現在は一般的に推奨されていません。
カテゴリー5:精神的・スピリチュアルな目的の呼吸法
瞑想やマインドフルネスと深く関連します。
1. マインドフルネス呼吸法
用途・効果:
「今、ここ」への意識集中
ストレス軽減、感情の安定
自己認識の向上、客観性の涵養
集中力・注意力向上
やり方:
楽な姿勢(座位が一般的)をとり、目を閉じるか半眼にします。
自分の自然な呼吸に意識を向けます。
息を吸うとき、鼻や口を通る空気の流れ、胸やお腹が膨らむ感覚に気づきます。
息を吐くとき、空気が外に出ていく感覚、胸やお腹がへこむ感覚に気づきます。
呼吸をコントロールしようとせず、ただ「観察」します。
思考や感情、雑念が浮かんできても、それに囚われず、判断せず、ただ気づき、再び呼吸に意識を戻します。
数分から始め、徐々に時間を延ばしていきます。
2. ヴィパッサナー瞑想における呼吸の観察
用途・効果:
自己観察による気づきの深化
心の浄化、苦しみからの解放(仏教的観点)
(マインドフルネスと共通する効果も多い)
やり方:
マインドフルネス呼吸法と非常に似ていますが、より微細な感覚(鼻孔の入り口での空気の触覚など)に集中し、変化し続ける現象をありのままに観察し続けることを重視します。専門的な指導の下で行われることが多いです。
まとめ
これらの呼吸法は、それぞれ異なるアプローチで心身に働きかけます。ご自身の目的や体調に合わせて、いくつかの呼吸法を試してみて、心地よいと感じるもの、効果を実感できるものを見つけてみてください。継続することが最も重要です。