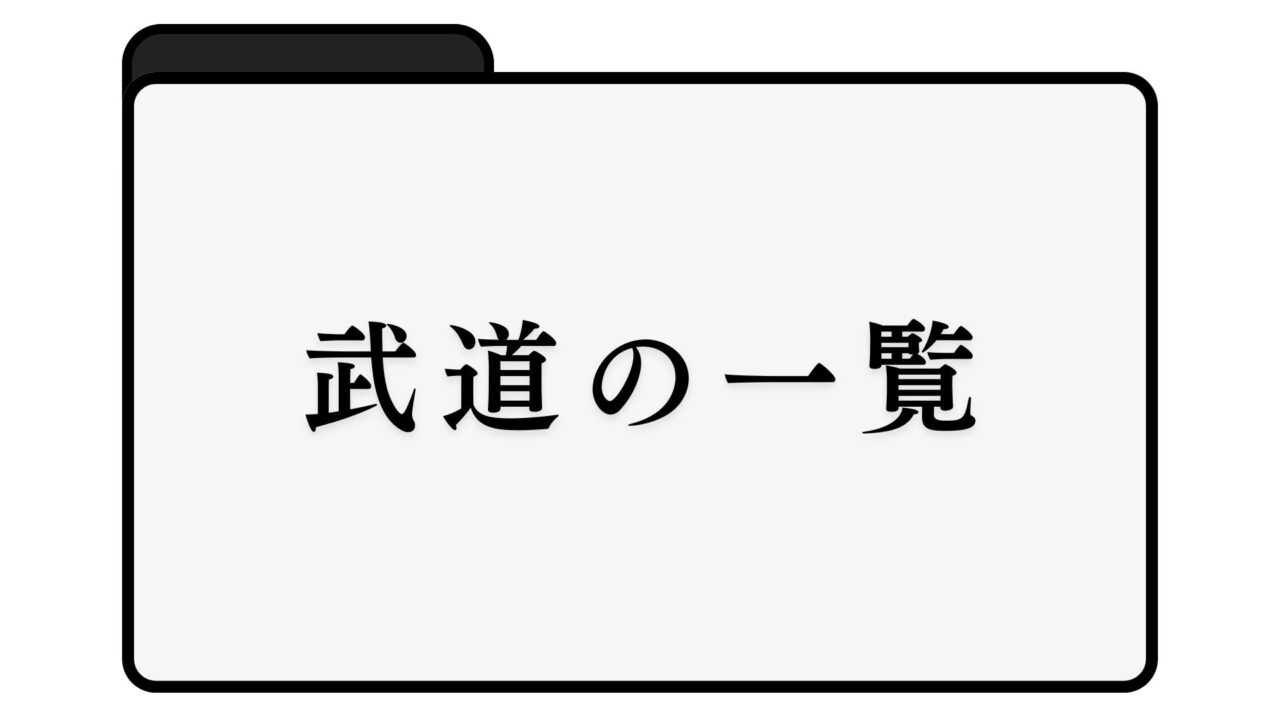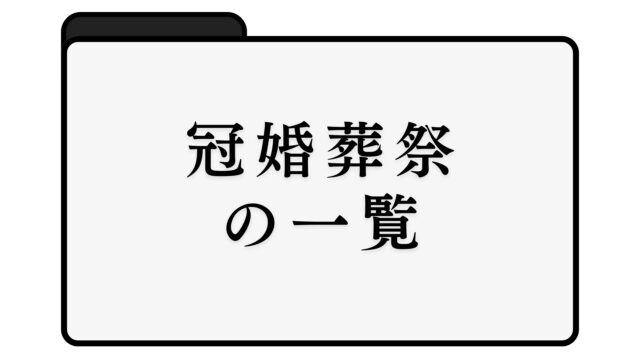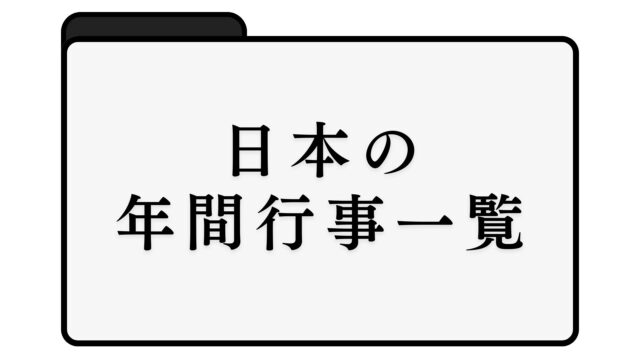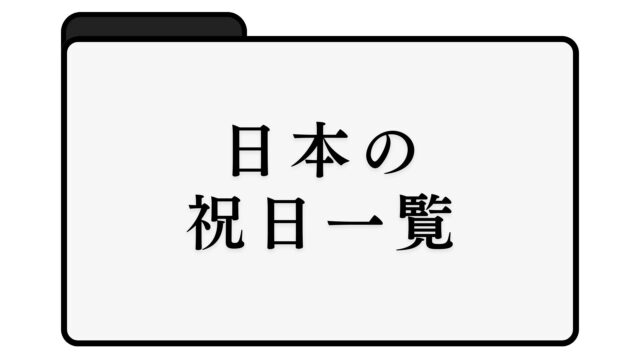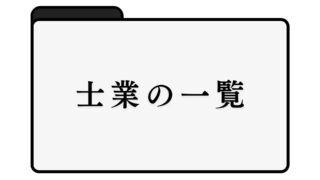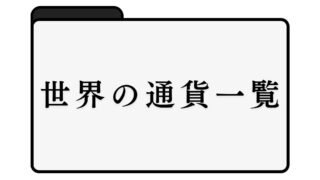今回は、心技体を鍛える武道の魅力と基本をまとめてみました。
日本には古来より受け継がれてきた多様な武道が存在し、それぞれが独自の技術体系、理念、そして精神性を持っています。
武道は単に強さを求めるだけでなく、礼節を重んじ、心身を鍛錬し、人格形成を目指す道でもあります。
この記事では、国内で広く稽古され、多くの人々に親しまれている代表的な武道をピックアップし、それぞれの特徴、主な技や稽古内容、理念、段位、稽古場所、使用する武具、そして競技性について分かりやすく解説します。
武道に興味がある方、これから始めてみたいと考えている方の参考になれば幸いです。
1. 剣道 (けんどう)
武道名: 剣道 (Kendo)
特徴:
防具を装着し、竹刀(しない)を用いて相手の有効打突部位(面・小手・胴・突き)を打突することで勝敗を競う武道。
「気・剣・体の一致」や「残心(ざんしん)」といった精神性が重視される。
礼法を重んじ、相手を尊重する心を養う。
生涯を通じて心身を鍛錬できる武道として幅広い年齢層に親しまれている。
主な技・稽古内容:
基本稽古: 素振り、足さばき、切り返し、打ち込み稽古(面打ち、小手打ち、胴打ち、突きなど)。
応用稽古: 掛かり稽古、地稽古、試合稽古。
形稽古: 日本剣道形(大刀7本、小太刀3本)。
理念・精神:
「剣の理法の修錬による人間形成の道」
礼儀作法、信義誠実、克己心、不動心、相手への敬意など。
段位・称号:
段位:初段~八段
称号:錬士、教士、範士
稽古場所・道場: 剣道場、体育館、学校の武道場など。
使用する武具・防具:
武具: 竹刀(しない)
防具: 面(めん)、小手(こて)、胴(どう)、垂(たれ)
剣道着、袴(はかま)
競技性・試合形式:
個人戦、団体戦がある。
試合時間内に有効打突を2本先取した方が勝ち(3本勝負)。1本のみの場合は1本勝ち。時間内に勝敗が決まらない場合は延長戦や引き分け、判定となることもある。
2. 柔道 (じゅうどう)
武道名: 柔道 (Judo)
特徴:
嘉納治五郎師範によって創始された、日本発祥の武道であり、オリンピック競技としても採用されている。
相手を投げたり、抑えたり、絞めたり、関節を極めたりして勝敗を競う。
「精力善用」「自他共栄」を基本理念とし、心身の力を最も有効に活用し、社会に貢献することを目指す。
受け身の練習が非常に重要視される。
主な技・稽古内容:
投げ技: 背負投、大外刈、内股、体落など多数。
固技: 抑込技(袈裟固、横四方固など)、絞技(裸絞、十字絞など)、関節技(腕緘、腕挫十字固など)。
受け身: 後ろ受け身、横受け身、前受け身、前方回転受け身。
稽古: 打ち込み、乱取り(自由練習)、形稽古(投の形、固の形など)。
理念・精神:
「精力善用 (せいりょくぜんよう)」: 心身の力を最も有効に活用すること。
「自他共栄 (じたくようえい)」: 相手を敬い感謝することで、互いに信頼し助け合い、自分だけでなく他人と共に栄えること。
段位・称号:
級位・段位:級は数字が小さくなるほど上位(例:5級~1級)、段は数字が大きくなるほど上位(初段~十段)。
称号:(講道館では廃止されているが、一部団体で使用)
稽古場所・道場: 柔道場(畳敷き)、体育館、学校の武道場など。
使用する武具・防具:
柔道着(白または青)、帯
競技性・試合形式:
個人戦、団体戦がある。
「一本」を取れば勝ち。一本に至らない技は「技あり」となり、技あり2つで「合わせ技一本」。試合時間内に一本が出ない場合は、技ありの数や指導(反則)の数で優勢勝ちが決まる。ゴールデンスコア方式の延長戦もある。
3. 弓道 (きゅうどう)
武道名: 弓道 (Kyudo)
特徴:
和弓を用いて矢を的に射る武道。的中だけでなく、射法(弓を引く一連の動作)の美しさや精神性が重視される。
「射法八節(しゃほうはっせつ)」と呼ばれる基本動作がある。
「真・善・美」の追求を理念とする。
静寂の中で自己と向き合い、集中力を高めることができる。
主な技・稽古内容:
基本動作: 射法八節(足踏み、胴造り、弓構え、打起し、引分け、会、離れ、残心)。
稽古: 巻藁(まきわら)稽古、的前(まとまえ)稽古、体配(たいはい:射を行う際の立ち居振る舞い)。
流派: 日置流、小笠原流など様々な流派が存在する。
理念・精神:
「真・善・美」の追求。
礼節、平常心、克己心、集中力、調和。
段位・称号:
段位:初段~十段
称号:錬士、教士、範士
稽古場所・道場: 弓道場(射場、安土、的場などから構成される)。
使用する武具・防具:
和弓(わきゅう)、矢(や)、弽(ゆがけ:弓を引く際に右手に装着する鹿革製の手袋)
弓道着、袴、胸当て(女性や一部男性が使用)
競技性・試合形式:
近的競技(28m先の的に対する的中を競う)、遠的競技(60m先の的に対する的中を競う)などがある。
的中数や、射形・体配の美しさなどが評価される場合もある。
4. 空手道 (からてどう)
武道名: 空手道 (Karatedo)
特徴:
沖縄発祥の武術を源流とし、主に手足(拳、足刀、手刀など)を使い、突き・蹴り・受けなどの技を繰り出す武道。
「形(かた)」と「組手(くみて)」が稽古の中心。
「寸止め(相手に当てる寸前で止める)」ルールと、「フルコンタクト(実際に打撃を当てる)」ルールなど、流派や団体によって競技形式が異なる。
礼節を重んじ、精神修養を目的とする。
主な技・稽古内容:
基本稽古: 立ち方、突き、蹴り、受け、移動稽古。
形稽古: 伝統的な一連の攻防の技を組み合わせた演武。多くの種類がある。
組手稽古: 約束組手(あらかじめ技を決めて行う)、自由組手(自由に技を攻防する)。
理念・精神:
「空手に先手なし」
礼節、忍耐、克己、勇気、謙譲の精神など。
「守礼の邦(しゅれいのくに)」の精神。
段位・称号:
級位・段位(流派・団体により異なる)
称号(流派・団体により異なる)
稽古場所・道場: 空手道場、体育館、学校の武道場など。
使用する武具・防具:
空手着、帯
組手試合ではメンホー(頭部保護具)、ボディプロテクター、拳サポーター、シンガードなどを着用する場合がある(ルールによる)。
競技性・試合形式:
形競技(形の正確さ、力強さ、気迫などを競う)と組手競技(ポイント制やKO制などルールは多様)がある。
オリンピック競技としても採用された。
5. 合気道 (あいきどう)
武道名: 合気道 (Aikido)
特徴:
植芝盛平翁によって創始された武道。
相手の攻撃力を利用し、円運動や呼吸力を用いて相手を制する技が中心。
試合形式の競技は行わず、技の理合いを理解し、心身を錬磨することを目的とする。
「和合の精神」「万有愛護の精神」を重視する。
主な技・稽古内容:
体捌き: 入身(いりみ)、転換(てんかん)などの体の動かし方。
投げ技: 四方投げ、入身投げ、呼吸投げ、天地投げなど。
固め技: 一教、二教、三教、四教、小手返しなど。
呼吸法: 呼吸力を養うための稽古。
武器技: 剣(木剣)、杖(じょう)を用いた技も稽古されることがある。
理念・精神:
「天地人和合の武道」「万有愛護の精神」
相手と争わず、調和し、導くことを目指す。
自己の完成、心身の鍛錬。
段位・称号:
級位・段位(団体により異なる)
称号(一部団体で使用)
稽古場所・道場: 合気道道場(畳敷き)、体育館など。
使用する武具・防具:
合気道着、帯
稽古内容により木剣、杖を使用。
競技性・試合形式:
基本的に試合形式の競技は行われない。演武会などで日頃の稽古の成果を披露する。
6. 少林寺拳法 (しょうりんじけんぽう)
武道名: 少林寺拳法 (Shorinji Kempo)
特徴:
宗道臣(そうどうしん)によって創始された、「人づくりの行」としての武道。
「剛法(突き、蹴り、受けなど)」と「柔法(抜き、逆技、固め技など)」の二つの技法体系を持つ。
「活人拳(人を活かす拳)」であり、護身術としての側面も強い。
「力愛不二(りきあいふに)」「自己確立」「自他共楽」を理念とする。
主な技・稽古内容:
基本: 構え、運歩法、突き、蹴り、受け。
剛法: 突技、蹴技、打技、防技、かわし身など。
柔法: 守法(逆技、固技)、抜手法、押圧法(整法の一部)など。
演武: 剛法と柔法を組み合わせて構成し、二人一組で演じる。
運用法: 防具を着用して行う実践的な攻防練習。
法話: 拳禅一如の教えに基づく講話。
理念・精神:
「力愛不二(りきあいふに)」: 力と愛は一体であり、両者を調和させる。
「自己確立(じこかくりつ)」: 自分を信じ、頼れる自分を確立する。
「自他共楽(じこきょうらく)」: 自分だけでなく、他人も共に幸せになることを目指す。
「拳禅一如(けんぜんいちにょ)」: 肉体と精神は一体であり、共に修行する。
段位・称号:
級位・段位
法階・武階
稽古場所・道場: 少林寺拳法の道院(どういん)、支部、体育館など。
使用する武具・防具:
道衣(どうい)、帯
運用法では胴、ヘッドガード、グローブなどを着用。
競技性・試合形式:
演武競技(二人一組または三人一組で行う技の正確さ、気迫、構成などを競う)。
過去には乱捕り(組手)競技も行われていたが、現在は演武が中心。
7. なぎなた
武道名: なぎなた (Naginata)
特徴:
長い柄の先に反りのある刃をつけた「なぎなた」という武具を使用する武道。
古くは戦場の武器として用いられ、江戸時代以降は特に女子の武芸として発展した。
打突部位(面、小手、胴、脛、突き)を正確に打突する技術を競う。
礼儀と気品を重んじ、美しい所作が求められる。
主な技・稽古内容:
基本稽古: 素振り、足さばき、打ち込み(中段、八相、下段などの構えから)。
形稽古: 全日本なぎなたの形、仕掛け応じなど。
試合稽古: 防具を着用して行う。
理念・精神:
心身の調和と気品の涵養。
礼儀、廉恥、忍耐、克己、勇気。
段位・称号:
級位・段位
称号:錬士、教士、範士
稽古場所・道場: なぎなた道場、体育館、学校の武道場など。
使用する武具・防具:
武具: なぎなた(競技用は主に樫の柄に竹製の刃部)
防具: 面、小手、胴、垂、脛当て
稽古着、袴
競技性・試合形式:
個人試合、団体試合がある。
有効打突(面、小手、胴、脛、咽喉への突き)によって勝敗を決める。
形競技もある。
8. 居合道 (いあいどう)
武道名: 居合道 (Iaido)
特徴:
日本刀(主に模擬刀を使用)を鞘に納めた状態から、仮想の敵に対して抜き打ちし、納刀するまでの一連の動作(形)を修練する武道。
「鞘の内(さやのうち)」の勝負とも言われ、抜刀の瞬間に勝敗が決するという緊張感がある。
精神集中と正確無比な刀の操作が求められる。
多くの古流と、全日本剣道連盟制定居合がある。
主な技・稽古内容:
形稽古: 座技、立技など様々な状況を想定した形を繰り返し稽古する。抜き付け、切り下ろし、血振り、納刀といった一連の動作を正確に行う。
精神修養: 集中力、平常心、残心などを養う。
理念・精神:
「常住坐臥(じょうじゅうざが)これ禅」
「鞘の内」の精神、平常心、克己心、不動心、礼節。
段位・称号:
段位:初段~十段(全日本剣道連盟の場合)、各流派で異なる場合もある。
称号:錬士、教士、範士(全日本剣道連盟の場合)
稽古場所・道場: 居合道場、剣道場、体育館など。
使用する武具・防具:
居合刀(模擬刀が一般的、真剣を使用する場合もある)、鞘
居合道着、袴、帯
競技性・試合形式:
試合形式(演武形式)があり、指定された形を演武し、その正確さ、気迫、品格などが審査される。
9. 相撲 (すもう)
武道名: 相撲 (Sumo)
特徴:
日本の国技であり、神事や祭礼とも深く結びついた伝統的な武道・格闘技。
土俵の上で、まわしを締めた二人の力士が組み合い、相手を土俵の外に出すか、足の裏以外の体の一部を土俵につけることで勝敗を決める。
「心・技・体」の充実が求められ、礼儀作法や伝統的な所作が重んじられる。
プロの「大相撲」が有名だが、アマチュア相撲も盛ん。
主な技・稽古内容:
基本動作: 四股(しこ)、鉄砲(てっぽう)、すり足。
決まり手: 押し出し、寄り切り、上手投げ、下手投げなど多数(大相撲では82手)。
稽古: 申し合い、ぶつかり稽古、三番稽古など。
理念・精神:
礼節、克己、忍耐、勇気、不動心。
「心・技・体」の錬磨。
段位・称号:
アマチュア相撲では段級位制がある。
大相撲では番付(横綱、大関、関脇、小結、前頭、十両など)で実力を示す。
稽古場所・道場: 相撲部屋(大相撲)、相撲道場、学校の土俵など。
使用する武具・防具:
まわし
競技性・試合形式:
トーナメント方式やリーグ戦などがある。
一対一の勝負で、相手を土俵外に出すか、足の裏以外を土俵につければ勝ち。
10. 杖道 (じょうどう)
武道名: 杖道 (Jodo)
特徴:
約128cmの杖(じょう)を用い、主に太刀(木刀を使用)を持つ相手を制圧することを目的とした武道。
古武道の一つであり、神道夢想流杖術を源流とする。
間合いの取り方や、杖の多様な操作法(突き、払い、打ちなど)が特徴。
形稽古が中心で、相手との調和や気迫が重視される。
主な技・稽古内容:
基本動作: 構え、体捌き、杖の操作(本手打ち、逆手打ち、返し突きなど)。
形稽古: 全日本剣道連盟制定杖道形(12本)、古流の形など。打太刀(太刀を持つ側)と仕杖(杖を持つ側)に分かれて行う。
理念・精神:
相手を傷つけずに制する「活人剣」ならぬ「活人杖」の精神。
礼節、克己心、平常心、気迫。
段位・称号:
段位:初段~八段(全日本剣道連盟の場合)
称号:錬士、教士、範士(全日本剣道連盟の場合)
稽古場所・道場: 剣道場、体育館など。
使用する武具・防具:
杖(じょう)、木刀(もくとう)
稽古着、袴
競技性・試合形式:
試合形式(演武形式)があり、指定された形を演武し、その正確さ、気迫、理合いの理解度などが審査される。
まとめ
日本の武道は、それぞれが独自の歴史と背景を持ち、技術だけでなく精神性の鍛錬を重んじています。
剣道、柔道、弓道、空手道、合気道、少林寺拳法、なぎなた、居合道、相撲、杖道など、ここで紹介した武道は、いずれも心身を鍛え、礼節を学び、豊かな人間性を育む道として、現代社会においても多くの人々にその価値が認められています。
武道を始めることは、体力向上や護身術の習得だけでなく、集中力や忍耐力、相手を敬う心など、日常生活にも活かせる多くのものを得られる素晴らしい機会となるでしょう。
興味を持った武道があれば、ぜひ一度道場の門を叩いてみてはいかがでしょうか!