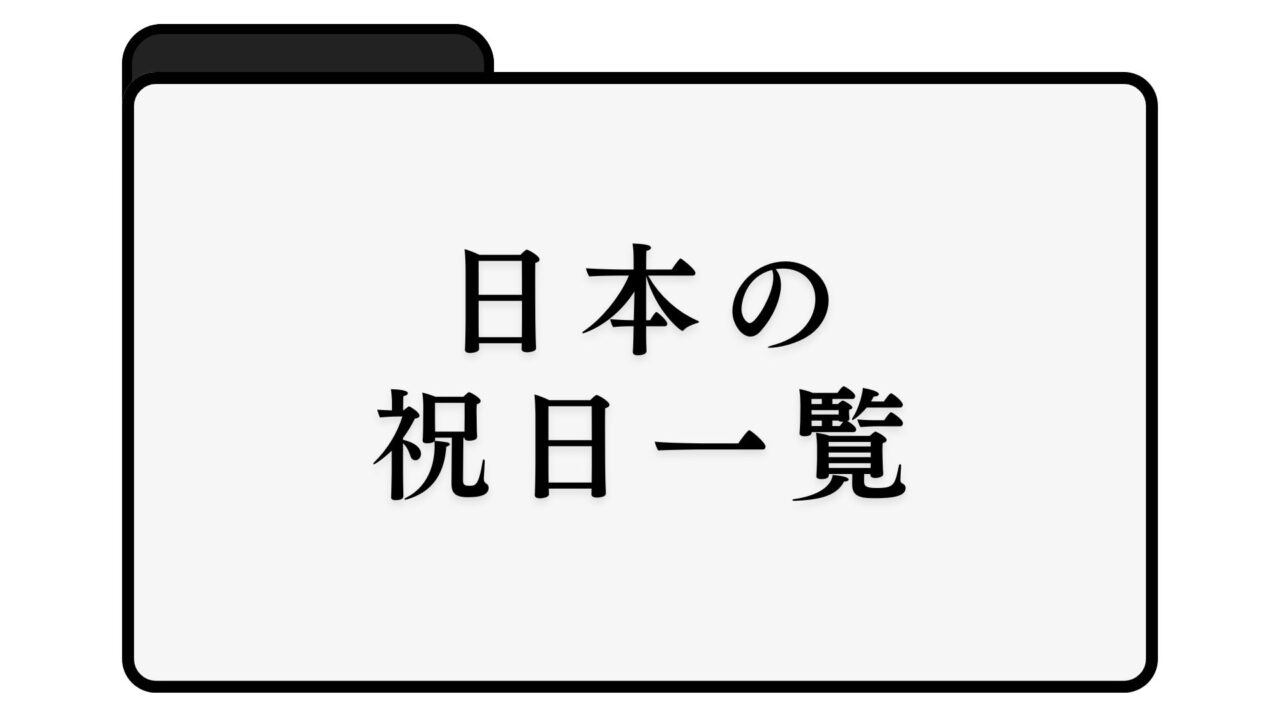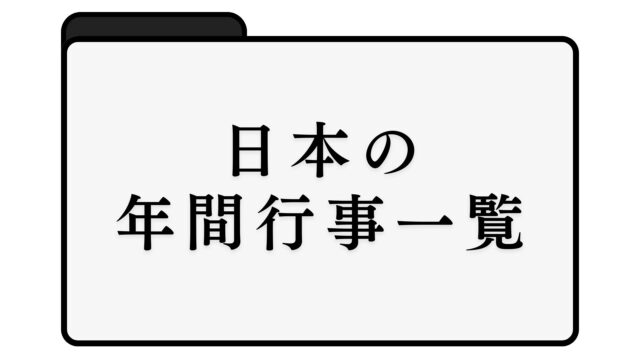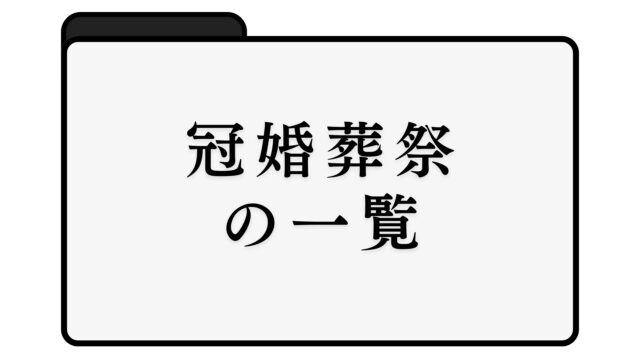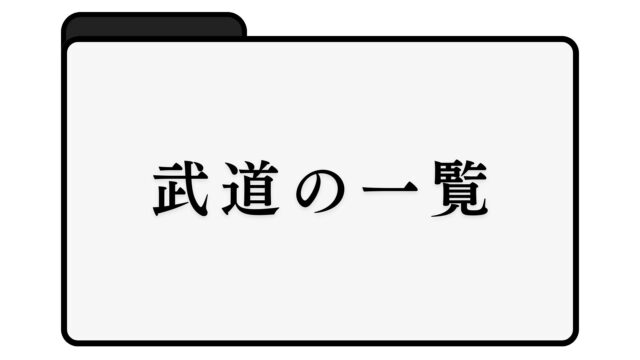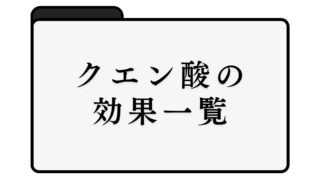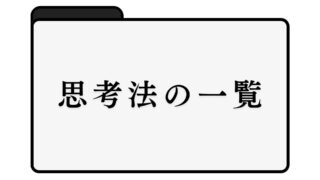以下は日本の祝日を月ごとに一覧化し、各祝日の特徴や逸話も添えた内容です。
1月
1.元日(1月1日)
意味・由来:新しい年を迎えることを祝い、1年の健康や平和を祈る日です。古代から続く風習が多く残ってます。
風習:初詣に行ったり、おせち料理を食べたり、年賀状を送ったりします。家族と静かに過ごす方が多い日でもあります。
特徴:日本人にとって最も重要な祝日のひとつです。
2.成人の日(1月の第2月曜日)
意味・由来:20歳になった方の大人としての自覚を促し、社会の一員としての責任を認識してもらう日です。
風習:各地で「成人式」が行われます。女性は振袖、男性はスーツや袴を着て式典に出席します。
特徴:華やかで希望に満ちた雰囲気が街中にあふれます。
2月
3.建国記念の日(2月11日)
意味・由来:日本という国ができたことをしのび、国を愛する気持ちを育てる日です。神武天皇の即位日が起源とされています。
風習:国旗を掲げるご家庭もあり、学校などでも国の歴史に関する学びが行われます。
特徴:国への感謝と誇りを考えるきっかけとなる日です。
4.天皇誕生日(2月23日)
意味・由来:今上天皇(徳仁天皇)のお誕生日をお祝いする日です。
風習:皇居では一般参賀が行われ、多くの国民が集まります(近年は制限されることもあります)。
特徴:皇室との距離を感じることができる、特別な祝日です。
3月
5.春分の日(3月20日頃)
意味・由来:昼と夜の長さがほぼ等しくなる節目の日で、自然や生き物を敬う日とされています。
風習:お彼岸の中日として、先祖のお墓参りに行くご家庭が多いです。
特徴:季節の変わり目を感じ、家族や自然への感謝を新たにする日です。
4月
6.昭和の日(4月29日)
意味・由来:昭和天皇の誕生日であり、昭和という時代を振り返り、未来を考える日です。
風習:この日からゴールデンウィークが始まるため、旅行や行楽に出かける方が多いです。
特徴:歴史を学び、平和の大切さを再確認する機会でもあります。
5月
7.憲法記念日(5月3日)
意味・由来:1947年の日本国憲法施行を記念する日です。
風習:テレビや新聞で憲法に関する特集が組まれたり、講演会などが行われたりします。
特徴:民主主義や人権の尊重について考える日です。
8.みどりの日(5月4日)
意味・由来:自然に親しみ、その恩恵に感謝する日です。もともとは昭和天皇が植物好きだったことにちなんでいます。
風習:公園や植物園で自然を楽しむイベントが開催されます。
特徴:自然環境への関心を高める日です。
9.こどもの日(5月5日)
意味・由来:こどもの健やかな成長を願い、お祝いする日です。古くは「端午の節句」として男子の健やかな育成を願っていました。
風習:鯉のぼりを立てたり、五月人形を飾ったり、柏餅やちまきを食べたりします。
特徴:家族の絆を深め、子どもたちを中心にした明るい日です。
6月
※祝日はありません。
7月
10.海の日(7月の第3月曜日)
意味・由来:海に囲まれた日本の恩恵に感謝し、海洋国としての繁栄を願う日です。
風習:海辺でのイベントやマリンスポーツが活発になります。
特徴:夏の訪れを感じさせる祝日です。
8月
11.山の日(8月11日)
意味・由来:「山に親しむ機会を得て、恩恵に感謝する」という目的で制定されました(2016年に新設)。
風習:登山やキャンプなど自然に触れる活動が多く行われます。
特徴:夏休み期間中でもあり、家族でアウトドアを楽しむ方が多い日です。
9月
12.敬老の日(9月の第3月曜日)
意味・由来:長年社会に尽くしてきた高齢者を敬愛し、その長寿を祝う日です。
風習:祖父母へのプレゼントや感謝の手紙を贈る習慣があります。
特徴:家族のつながりや世代間の交流を大切にする日です。
13.秋分の日(9月23日頃)
意味・由来:祖先を敬い、亡くなった方々をしのぶ日です。昼と夜がほぼ同じ長さになる自然の節目でもあります。
風習:春分の日と同様、お彼岸のお墓参りが行われます。
特徴:しっとりとした落ち着いた雰囲気の祝日です。
10月
14.スポーツの日(10月の第2月曜日)
意味・由来:スポーツに親しみ、健康な心と体を育む日です。元は「体育の日」として、1964年の東京オリンピックに由来しています。
風習:学校や地域で運動会・スポーツ大会が行われます。
特徴:秋のさわやかな気候の中、体を動かすには最適な日です。
11月
15.文化の日(11月3日)
意味・由来:自由と平和を愛し、文化をすすめる日です。日本国憲法の公布日にもあたります。
風習:文化祭、美術展、表彰式(文化勲章など)が各地で開催されます。
特徴:芸術や学問を楽しむ、知的で静かな祝日です。
16.勤労感謝の日(11月23日)
意味・由来:働くことをたっとび、生産活動に感謝し合う日です。古代の「新嘗祭(にいなめさい)」がルーツです。
風習:農作物の収穫を祝い、働くすべての人に感謝を伝えることが重視されます。
特徴:家族でゆったりと過ごしながら、日頃の努力に感謝する日です。
12月
※祝日はありません。かつては12月23日が「天皇誕生日」でした。
まとめ
祝日は多いに越したことはありませんが、なかなか増やせないのには理由があって、株価に影響を与えるからだそうです。
稼働日が減ることでその分業績に影響が出るとのことで、なかなか祝日を増やすことは難しいようなんです。
余談ですが大谷翔平ノ誕生日は祝日にするべきだ。
ってじっちゃんが言ってました。
それでは良い祝日を!