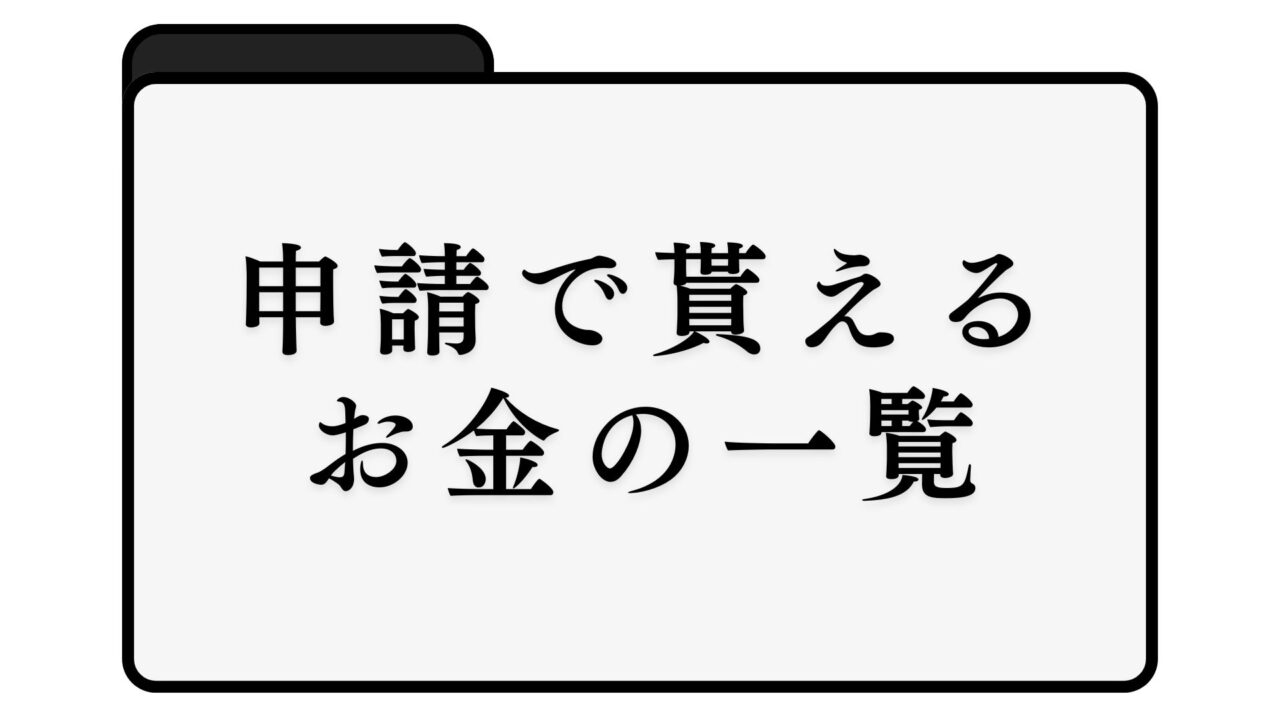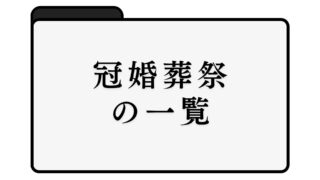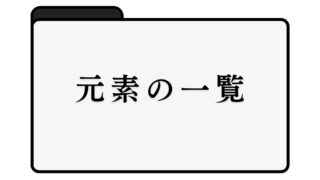日本では、申請により受け取ることができる給付金や補助金が多数存在します。
以下に主なものをカテゴリー別にまとめました。
出産・子育てに関する給付金・補助金
1.出産手当金
出産手当金は、勤務先の健康保険に加入している被保険者が、出産のために仕事を休んだ際に支給される手当です。
支給対象者
以下の条件を満たす方が対象となります。
健康保険の被保険者であること
勤務先の健康保険に加入していることが必要です。パートやアルバイトでも、被保険者であれば対象となります。
妊娠4ヶ月(85日)以上の出産であること
妊娠4ヶ月以降の出産、流産、早産、死産、人工妊娠中絶などが含まれます。
出産のために仕事を休んでいること
産前産後休業中で、給与の支払いがない、または出産手当金の日額より少ない場合が該当します。
支給期間
出産日を基準として、以下の期間が支給対象となります。
産前
出産予定日の42日前(多胎妊娠の場合は98日前)から出産日まで。
産後
出産日の翌日から56日目まで。
出産が予定日より遅れた場合、その分支給期間も延長されます。
支給額
1日あたりの支給額は、以下の計算式で求められます。
支給開始日以前の12ヶ月間の標準報酬月額の平均額 ÷ 30 × 2/3
これにより、給与のおおよそ3分の2が支給されます。
申請手続き
出産手当金の申請は、以下の手順で行います。
申請書の入手
加入している健康保険組合や協会けんぽから「出産手当金支給申請書」を入手します。
必要事項の記入
申請書に必要事項を記入し、医師または助産師の証明を受けます。
事業主の証明
勤務先の担当部署に申請書を提出し、休業期間や給与の支払い状況についての証明を受けます。
申請書の提出
必要書類を添えて、健康保険組合や協会けんぽに提出します。
申請期限は、産休開始日の翌日から2年間です。
注意点
退職後の受給
退職日までに1年以上健康保険に加入しており、退職日に産前休業中である場合、退職後も出産手当金を受け取ることができます。
給与との調整
休業中に給与が支払われる場合、出産手当金の日額より少ない場合は差額が支給されますが、日額以上の場合は支給されません。
国民健康保険の場合
自営業やフリーランスなどで国民健康保険に加入している場合、出産手当金は支給されません。
ただし、一部の国民健康保険組合では独自に支給している場合があります。
詳細や最新の情報については、加入している健康保険組合や勤務先の担当部署にお問い合わせください。
2.児童手当
児童手当は、子育て家庭の経済的負担を軽減し、児童の健やかな成長を支援するための制度です。
支給対象者
日本国内に住所を有する中学校修了前(15歳到達後、最初の3月31日まで)の児童を養育している方が対象です。
支給額
3歳未満
月額15,000円
3歳以上小学校修了前
第1子・第2子は月額10,000円、第3子以降は月額15,000円
中学生
月額10,000円
なお、所得制限限度額以上の場合、特例給付として一律月額5,000円が支給されます。
申請手続き
申請時期
お子さんが生まれたときや他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出する必要があります。
必要書類
申請者の健康保険証の写し、本人確認書類、振込先口座の通帳などが必要です。
提出先
お住まいの市区町村の担当窓口へ提出します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受け取れなくなるため、早めの手続きをお勧めします。
注意点
現況届の提出
毎年6月に、受給資格の継続を確認するための現況届の提出が必要です。提出がない場合、手当が停止されることがあります。
所得制限
受給者の所得が一定額以上の場合、特例給付として月額5,000円が支給されます。
公務員の場合
勤務先を通じての申請となります。
詳細や最新の情報については、お住まいの市区町村の担当窓口や公式ウェブサイトでご確認ください。
3.児童扶養手当
児童扶養手当は、主にひとり親家庭の生活の安定と子どもの健全な育成を支援するための制度です。
支給対象者
以下のいずれかの状態にある子ども(18歳到達後最初の3月31日まで、または一定の障害がある場合は20歳未満)を養育している方が対象となります。
・父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない子ども
・父または母が死亡、重度の障害状態にある、または生死が明らかでない子ども
・父または母から1年以上遺棄されている子ども
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
・父または母が1年以上拘禁されている子ども
・婚姻によらないで生まれた子ども
・その他、父または母が不明である場合など
支給額
手当の額は、所得や子どもの人数に応じて変動します。所得が一定額以下の場合、全額支給となり、所得が増加すると一部支給となります。
具体的な支給額や所得制限については、お住まいの自治体の窓口で確認することをお勧めします。
申請手続き
手当を受けるためには、以下の手順で申請を行います。
申請窓口
お住まいの市区町村の福祉担当窓口で手続きを行います。
必要書類
申請書のほか、戸籍謄本、所得証明書、本人確認書類、振込先口座の通帳などが必要となります。
詳細は自治体の窓口で確認してください。
申請期限
手当は申請した翌月分から支給されます。
遡っての支給は行われないため、該当する場合は速やかに申請することが重要です。
注意点
所得制限
受給者やその扶養義務者の所得が一定額以上の場合、手当の全部または一部が支給停止となる場合があります。
現況届の提出
毎年8月に、受給資格の継続を確認するための現況届を提出する必要があります。これを怠ると手当が停止されることがあります。
他の手当との併給
児童手当など、他の手当との関係で支給額が調整される場合があります。
詳細や最新の情報については、お住まいの市区町村の福祉担当窓口や公式ウェブサイトでご確認ください。
4.高等学校等就学支援金
高等学校等就学支援金制度は、高等学校等に通う生徒の授業料負担を軽減するための国の制度です。
所得要件を満たす世帯に対し、授業料に充てるための支援金が支給されます。
対象者
以下の要件を満たす生徒が対象となります。
・在学要件: 日本国内に在住し、高等学校等に在学していること。
・所得要件: 保護者等の所得が一定の基準を満たすこと。具体的には、保護者等の市町村民税の課税所得額などに基づき判定されます。
支給額
支給額は、授業料の額を上限として、学校の種別や課程に応じて設定されています。詳細な支給額については、文部科学省の公式サイトで確認できます。
申請手続き
申請は、原則として入学時の4月に行います。必要な書類を学校を通じて提出します。具体的な手続きや提出期限については、在学する学校からの案内に従ってください。
注意点
・所得確認: 地方住民税の情報を基に所得確認が行われるため、未申告の場合は事前に申告を行う必要があります。
・変更の報告: 保護者等の収入に変更があった場合や、離婚・死別、養子縁組等で保護者等が変更になった場合は、速やかに学校を通じて所定の手続きを行ってください。
詳細や最新の情報については、文部科学省の公式ウェブサイトをご確認ください。
医療・健康に関する給付金・補助金
5.高額療養費制度
高額療養費制度は、1か月(暦月)における医療費の自己負担額が一定の上限額を超えた場合に、その超過分が払い戻される公的医療保険の制度です。
自己負担限度額
自己負担限度額は、年齢や所得に応じて設定されています。
例えば、70歳未満の方の場合、所得区分に応じて以下のようになります。
・区分ア(標準報酬月額83万円以上): 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
・区分イ(標準報酬月額53万~79万円): 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
・区分ウ(標準報酬月額28万~50万円): 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
・区分エ(標準報酬月額26万円以下): 57,600円
・区分オ(低所得者): 35,400円
これらの区分や詳細については、全国健康保険協会のウェブサイトで確認できます。
申請手続き
高額療養費の支給を受けるには、以下の手順で申請を行います
・申請書の入手: 加入している医療保険の保険者(例:全国健康保険協会、健康保険組合、市区町村の国民健康保険窓口など)から「健康保険高額療養費支給申請書」を入手します。
・必要事項の記入: 申請書に必要事項を記入し、医療機関の領収書などの必要書類を添付します。
・申請の提出: 記入済みの申請書と添付書類を保険者に提出します。
申請後、医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)の審査を経て、支給が決定されます。支給までには診療月から3か月以上かかる場合があります。
限度額適用認定証の利用
高額な医療費が事前に予想される場合、「限度額適用認定証」を事前に取得し、医療機関の窓口で提示することで、自己負担額を限度額までに抑えることが可能です。
この認定証の交付手続きについては、加入している医療保険の保険者にお問い合わせください。
注意点
世帯合算
同一世帯内で同じ月に複数の方が医療費を支払った場合、自己負担額を合算して高額療養費の対象とすることができます。
多数該当
過去12か月間に3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目以降の自己負担限度額が引き下げられる制度があります。
対象外費用
差額ベッド代や食事代など、保険適用外の費用は高額療養費の対象外となります。
詳細や最新の情報については、厚生労働省の公式ウェブサイトをご確認ください。
6.傷病手当金
傷病手当金は、被保険者が業務外の病気やケガで仕事を休み、給与が十分に受けられない場合に、生活を支援するための制度です。
支給要件
以下の条件をすべて満たす場合に支給されます。
・業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること: 業務上や通勤途上の事故などは労災保険の対象となるため、傷病手当金の対象外です。
・仕事に就くことができないこと: 医師の診断により、従事している業務ができない状態であると判断されることが必要です。
・連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと: 最初の3日間(待期期間)は連続している必要があり、有給休暇や公休日も含まれます。4日目以降の就業不能日について支給対象となります。
・休業した期間について給与の支払いがないこと: 休業期間中に給与が支払われていない、または支払われた給与が傷病手当金の額より少ない場合に支給されます。
支給額
1日あたりの支給額は、以下の計算式で求められます。
・支給開始日以前の12ヶ月間の各標準報酬月額の平均額 ÷ 30日 × 2/3
ただし、支給開始日以前の加入期間が12ヶ月に満たない場合は、以下のいずれか低い額が使用されます。
・支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
・標準報酬月額の平均値(令和7年3月31日以前は30万円、令和7年4月1日以降は32万円)
支給期間
支給開始日から通算して1年6ヶ月間が支給期間となります。
申請手続き
傷病手当金の申請には、「健康保険傷病手当金支給申請書」を事業主および医師の証明を受けて、協会けんぽに提出します。
注意点
退職後も一定の条件を満たせば、引き続き傷病手当金を受け取ることが可能です。
出産手当金や障害厚生年金など、他の給付金との関係で支給額が調整される場合があります。
詳細や最新の情報については、全国健康保険協会の公式ウェブサイトをご確認ください。
7.障害年金
障害年金は、病気やけがにより一定の障害状態となった場合に、生活を支援するための公的年金制度です。
日本の障害年金には、主に「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。
障害基礎年金
対象者
以下のいずれかに該当する方
・国民年金の被保険者期間中に初診日がある方
・20歳前または60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に初診日がある方
受給要件
・初診日の前日において、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が、被保険者期間の3分の2以上あること。ただし、初診日が令和8年4月1日前の場合、初診日に65歳未満であれば、初診日の前日において、直近1年間に保険料の未納がなければ要件を満たします。
・障害認定日において、障害等級表の1級または2級に該当する障害の状態であること。
障害厚生年金
対象者
・厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある方。
受給要件
・初診日の前日において、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が、被保険者期間の3分の2以上あること。ただし、初診日が令和8年4月1日前の場合、初診日に65歳未満であれば、初診日の前日において、直近1年間に保険料の未納がなければ要件を満たします。
・障害認定日において、障害等級表の1級から3級に該当する障害の状態であること。
年金額
・1級: 報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者の加給年金額(234,800円)
年金ポータル
・2級: 報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金額(234,800円)
年金ポータル
・3級: 報酬比例の年金額(最低保証額612,000円)
年金ポータル
申請手続き
必要書類
・年金請求書
・年金ポータル
・医師の診断書
・病歴・就労状況等申立書
・その他、必要に応じた書類
申請窓口: お近くの年金事務所または街角の年金相談センターで手続きを行います。
注意点
障害年金の受給には、初診日や保険料納付状況、障害の程度など複数の要件があります。
申請には詳細な書類が必要となるため、事前に必要書類を確認し準備を進めることが重要です。
申請手続きや受給要件について不明な点がある場合は、専門家や年金事務所に相談することをお勧めします。
詳細や最新の情報については、日本年金機構の公式ウェブサイトをご確認ください。
住宅に関する給付金・補助金
8.こどもエコすまい支援事業
こどもエコすまい支援事業は、子育て世帯や若者夫婦世帯による高い省エネ性能(ZEHレベル)を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援を行う制度です。
この事業は、エネルギー価格高騰の影響を受けやすい世帯の省エネ投資を下支えし、2050年のカーボンニュートラルの実現を目指しています。
補助対象者
注文住宅の新築
建築主が子育て世帯または若者夫婦世帯であること。
新築分譲住宅の購入
購入者が子育て世帯または若者夫婦世帯であること。
リフォーム
世帯を問わず、全ての世帯が対象。
子育て世帯および若者夫婦世帯の定義
子育て世帯
申請時点において、18歳未満(令和4年4月1日時点で)の子を有する世帯。
若者夫婦世帯
申請時点において夫婦であり、令和4年4月1日時点でいずれかが39歳以下である世帯。
補助額(補助上限)
注文住宅の新築および新築分譲住宅の購入
1住戸につき100万円。
リフォーム
実施する補助対象工事および工事発注者の属性等に応じて5万円から60万円。
対象期間
契約日の期間
契約日の期間は問いません。
対象工事の着手期間
2022年11月8日以降。
交付申請期間
2023年3月31日から予算上限に達するまで(遅くとも2023年12月31日まで)。
注意点
・補助金の申請手続きや受け取りと一般消費者への還元は、「こどもエコすまい支援事業者」が行います。
・補助対象者である一般消費者が直接申請をすることはできません。
詳細や最新の情報については、こどもエコすまい支援事業の公式ウェブサイトをご確認ください。
9.ZEH(ゼッチ)補助金
ZEH(ゼッチ、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)補助金は、省エネルギー性能が高く、再生可能エネルギーを活用する住宅の普及を促進するための制度です。
2025年度(令和7年度)における補助金の概要は以下のとおりです。
補助金額
ZEH住宅
1戸あたり55万円
ZEH+住宅
1戸あたり90万円
追加補助
以下の要件を満たす場合、追加の補助が受けられます。
蓄電システムの導入
2万円/kWh(上限20万円/台)
低炭素化に資する素材の使用
一定量以上の使用で追加補助
先進的再エネ熱利用技術の活用
対象設備の導入で追加補助
申請方法
補助金の申請は、住宅の建築や販売を行う事業者が行います。そのため、ZEH対応の住宅を検討されている場合は、該当の事業者に補助金の利用について相談することをお勧めします。
注意点
申請期間
2025年度の申請受付は、例年通りであれば5月頃から開始される見込みです。詳細なスケジュールは公式発表を確認してください。
併用不可の補助金
子育てグリーン住宅支援事業の補助金(60万円)とは併用できません。どちらの補助金が適用可能か、事前に確認が必要です。
対象要件
補助金を受けるためには、住宅が定められたZEH基準を満たす必要があります。
具体的な基準については、公式サイトや事業者に確認してください。
最新の情報や詳細については、公式ウェブサイトや関係機関の発表を随時確認することをお勧めします。
教育・資格取得に関する給付金・補助金
10.教育訓練給付制度
教育訓練給付制度は、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を目的とした制度です。
一定の条件を満たす方が、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講・修了した場合、教育訓練経費の一部が給付金として支給されます。
専門実践教育訓練
対象: 中長期的なキャリア形成に資する教育訓練
支給額
・教育訓練経費の50%(年間上限40万円)を受講中6か月ごとに支給
・資格取得等をし、訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合、追加で教育訓練経費の20%(年間上限16万円)を支給
さらに、訓練修了後の賃金が受講開始前と比較して5%以上上昇した場合、追加で教育訓練経費の10%(年間上限8万円)を支給
備考:令和6年10月以降に開講する講座が対象
特定一般教育訓練
対象
速やかな再就職や早期のキャリア形成に資する教育訓練
支給額
教育訓練経費の40%(上限20万円)を訓練修了後に支給
資格取得等をし、訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合、追加で教育訓練経費の10%(上限5万円)を支給
備考:令和6年10月以降に開講する講座が対象
一般教育訓練
対象
雇用の安定や就職促進に資する教育訓練
支給額
教育訓練経費の20%(上限10万円)を訓練修了後に支給
受給要件
受給資格の有無や詳細な要件については、お住まいを管轄するハローワークにお問い合わせください。
申請手続き
受講前であれば受講開始前にハローワークで受給資格の確認を行います。
受講・修了しているのであれば、指定された教育訓練を受講し修了します。
申請
訓練修了後、必要書類を揃えてハローワークに支給申請を行います。
詳細や最新の情報については、厚生労働省の公式ウェブサイトをご確認ください。
その他の給付金・補助金
11.結婚助成金
結婚助成金(正式名称:結婚新生活支援事業費補助金)は、新婚世帯の経済的負担を軽減し、結婚を促進することを目的とした国の制度です。
この補助金は、結婚に伴う新居の取得費用や引っ越し費用など、新生活のスタートに必要な費用の一部を支援するものです。
対象となる費用
新居の住居費(購入費、家賃、敷金・礼金、共益費、仲介手数料など)
ブラプラウェディング|フリープランナー掲載数No.1
新居への引っ越し費用(引っ越し業者や運送業者への支払い、荷造り費用など)
ブラプラウェディング|フリープランナー掲載数No.1
受給条件
夫婦ともに婚姻日において39歳以下であること
世帯所得が400万円未満であること(奨学金返済がある場合、その年間返済額を所得から差し引くことが可能)
補助金を実施している市区町村に新居を構え、住民登録を行っていること
過去に同様の補助金を受けていないこと
申請する年度内に対象となる支払いが完了していること
補助金額
夫婦ともに29歳以下の場合:最大60万円
上記以外の場合:最大30万円
申請方法
申請は、新居を構える市区町村の役所窓口で行います。申請期間や必要書類は自治体によって異なるため、事前に該当自治体の公式ウェブサイトや窓口で確認することが重要です。
ブラプラウェディング|フリープランナー掲載数No.1
注意点
すべての市区町村がこの補助金を実施しているわけではありません。居住予定の自治体が制度を導入しているか確認が必要です。
対象となる費用や条件は自治体によって異なる場合があります。最新の情報を自治体の公式サイトなどで確認しましょう。
申請期限や手続き方法を事前に把握し、必要書類を揃えて期限内に申請することが重要です。
結婚助成金を活用することで、新生活の経済的負担を軽減し、スムーズなスタートを切ることができます。詳細については、居住予定の市区町村の公式ウェブサイトや窓口で確認してください。
12.塾代助成事業
大阪市が実施している「習い事・塾代助成事業」は、子育て世帯の経済的負担を軽減し、子どもたちに学習やスポーツ、文化活動の機会を提供することを目的とした制度です。
この事業では、大阪市内在住の小学5年生から中学3年生を対象に、学習塾、家庭教師、文化・スポーツ教室などの学校外教育にかかる費用を月額1万円を上限に助成します。
対象者
大阪市内に住む小学5年生から中学3年生までの子どもを養育する保護者が対象です。ただし、里親や児童福祉施設等に措置または委託されている中学生は一部対象外となります。
助成内容
対象となる学校外教育の費用を、月額1万円を上限に助成します。利用可能な教室は、大阪市習い事・塾代助成事業に登録されている学習塾、家庭教師、文化・スポーツ教室などで、オンライン学習塾なども含まれます。
申請方法
助成を受けるには申請が必要です。
申請はオンラインまたは郵送で行えます。
申請受付の開始時期や詳細については、大阪市の公式ウェブサイトで案内されます。
例えば、令和7年度分(令和7年4月~令和8年3月利用分)の申請受付は、令和6年12月21日から開始されました。
注意点
申請期限を過ぎると、利用開始月が遅れる場合があります。
申請に関する詳細や最新情報は、大阪市の公式ウェブサイトで確認してください。
この助成事業を利用することで、子どもたちの学習やスポーツ、文化活動の機会を広げることができます。
まとめ
日本は申請することで色々な助成金などを受け取ることができます。
各地域毎に対象者や申請方法が異なるので、行政で確認してもらえるものはもらいましょう!