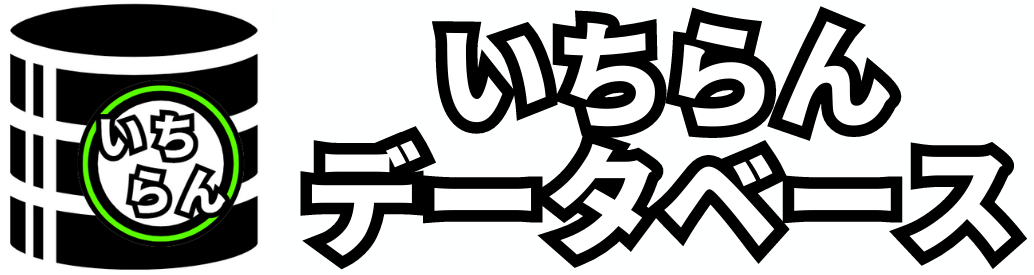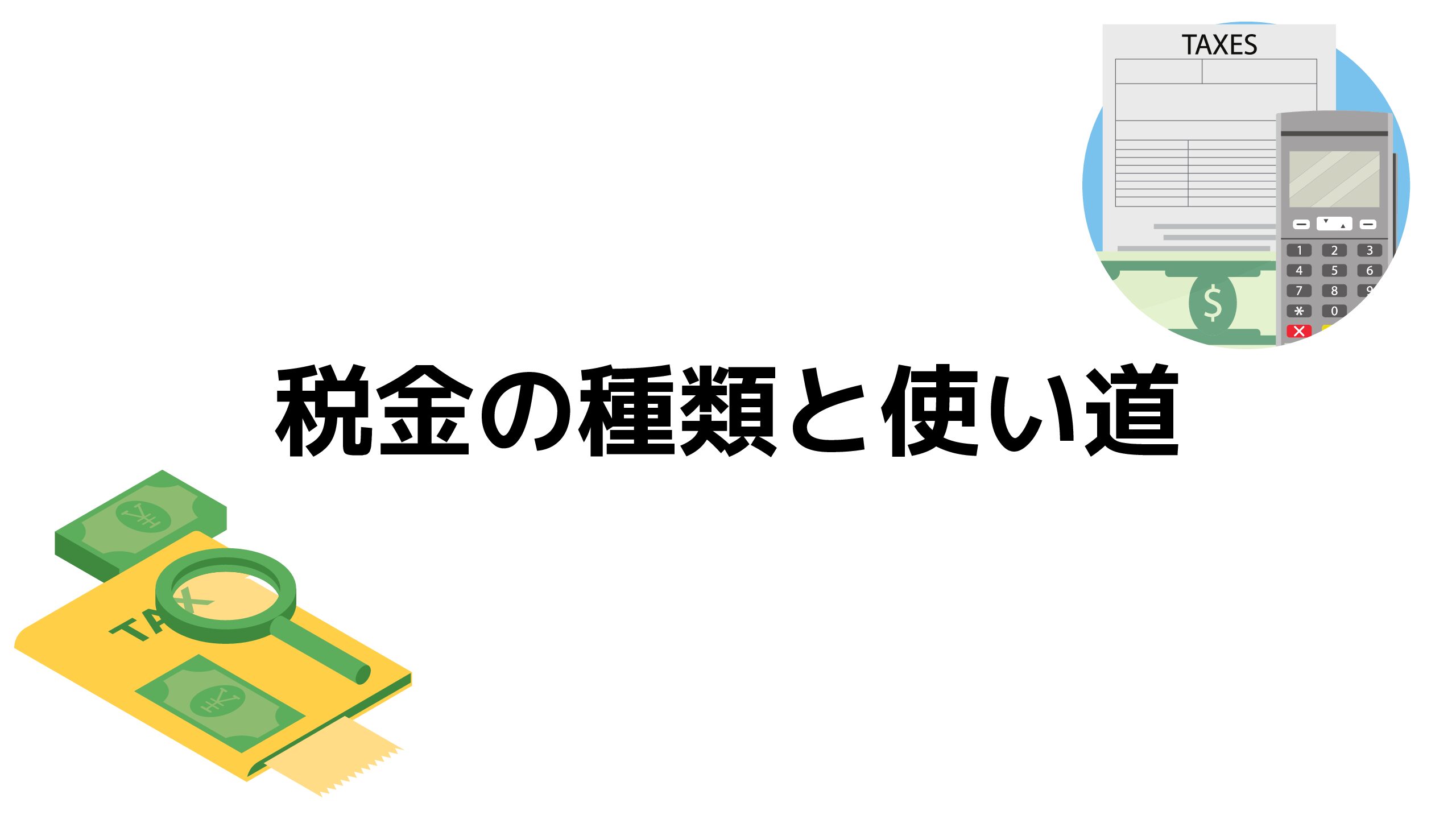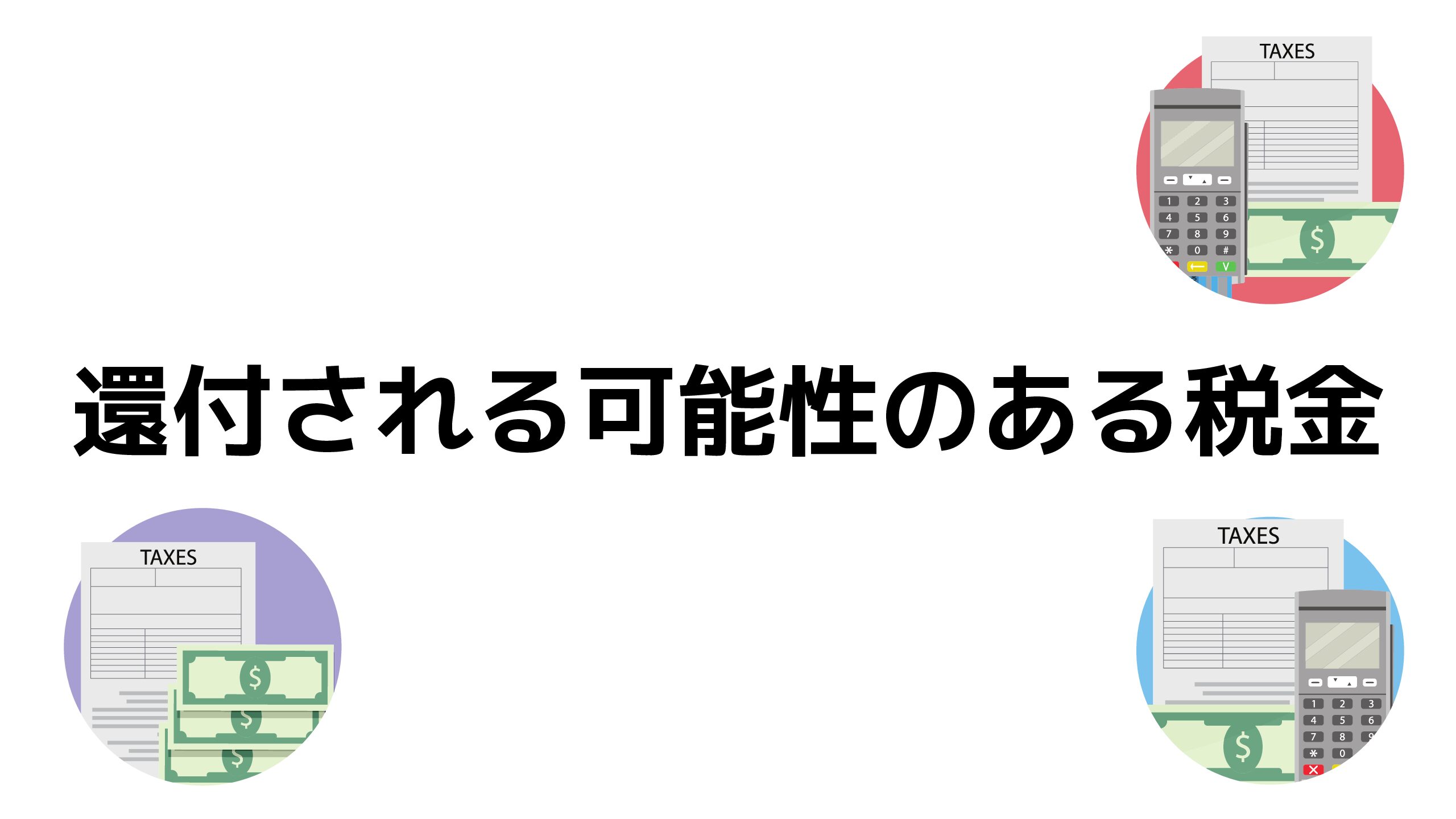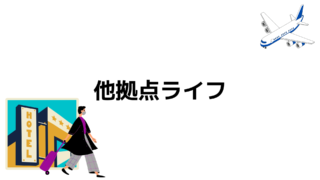年金の種類は2種類
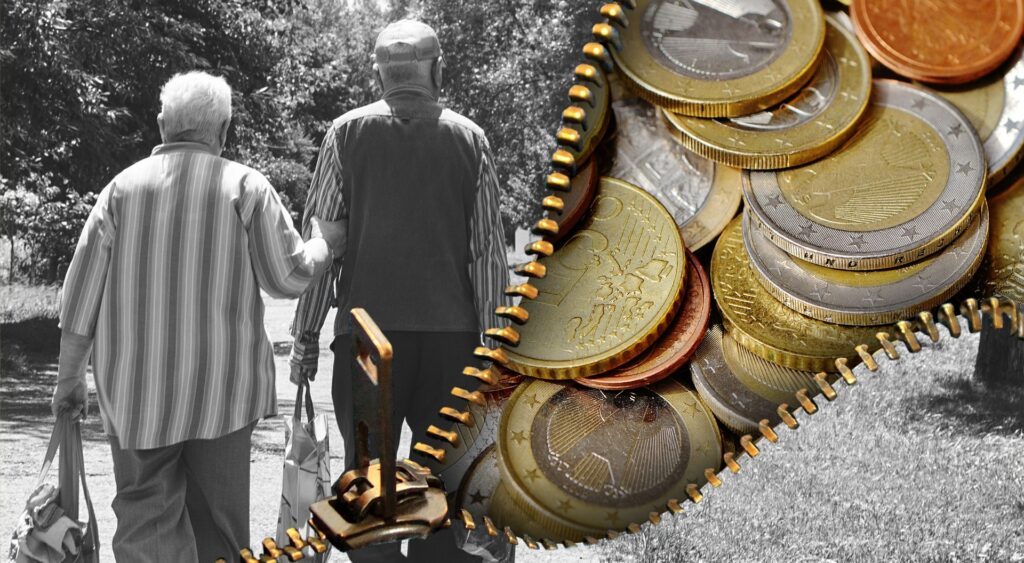
年金には公的年金と私的年金があり、主な違いは管轄組織の違いです。
年金保険料を納付するのを企業で行うか個人で行うかが主な違いとなります。
公的年金と私的年金の種類については下記で解説します。
公的年金
公的年金とは、国が運営・管理している年金制度です。
原則、満20歳以上60歳未満の日本に住む人が加入できる、国民年金と会社員や公務員が加入する厚生年金があります。
共済年金については2015年10月までは公務員専用でしたが、厚生年金に統一されました。
| 国民年金 | 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人 |
|---|---|
| 厚生年金 | 厚生年金に加入する企業に勤務する人や公務員の人 |
| 共済年金 | 公務員や私立教職員専用でしたが2015年10月以降厚生年金に統一されました |
国民年金
国民年金は、収入の所得に関係なく定額で給与から天引きされます。
国民年金の被保険者(受給時対象者)は第1号〜第3号に分かれており、下記です。
| 第1号被保険者 | 農業・学生・フリーター・無職の人が対象で、保険料を個人で納付 |
|---|---|
| 第2号被保険者 | 厚生年金に加入している企業に勤めている人が対象で保険料は給与天引 |
| 第3号被保険者 | 第2号被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満で年収が130万円以下の人が対象で保険料は国民年金制度が負担 |
経済的に保険料を支払うことが難しい場合は納付猶予制度や免除制度を利用することもできます。
厚生年金
厚生年金は会社員や公務員・私立教職員が加入する制度で国民年金と同じく給与天引きです。
また、厚生年金保険料は給与に応じて納付額が変動します。
給与が高額なほど納付する保険料も高額になりますが、受給時に受け取れる金額も上がります。
厚生年金保険料は納付する金額を加入者の従業員と勤務先で折半し納付します。
共済年金 ※2015年10月1日に厚生年金と統合済み
共済年金は、公務員や私立教職員などが加入していた年金制度でしたが、厚生年金と統合され廃止となりました。
公的年金の保険料は所得税を計算する際の「社会保険料控除」の対象となるので、その分、課税の対象となる所得が減ることとなり、所得税が少なくなります。
公的年金のメリット
- 老後資金を得られる
- 万が一自分が働けなくても家族が受給できる
- 万が一自分が亡くなっても家族が受給できる
- 労使折半で負担軽減措置がされる
- 経済的に支払いが難しい場合、納付猶予または免除制度を受けられる
公的年金のデメリット
- 国民年金は固定なので収入に関係なく天引きされる
- 厚生年金は収入に応じて納付金額が上がる
- 受給できる年齢制限と条件がある
私的年金
私的年金とは、個人で自主的に積み立てる年金制度で企業が福利厚生の一環として導入している場合があります。
種類も豊富で個人が自主的に積み立てることができるiDeCoや、企業の就業規則で定められている場合加入できる確定拠出制度などがありますので下記で紹介します。
企業年金
企業年金は、企業が従業員のために福利厚生で導入するものです。
従業員が定年退職後などに受け取れるように企業で毎月積み立てている場合がほとんどです。
企業年金には確定給付企業年金と企業方確定拠出年金などがあり、民間の金融機関に運用を委託する場合がほとんどです。
iDeCo
https://ichirandatabase.com/ideco-nisa/
iDeCoは、個人が任意で積み立てることができる個人型確定拠出年金制度で自分で運用商品などを選択し利益を出すことができます。
金融機関や保険会社、証券会社などが取り扱っており、運用商品もそれぞれで異なるので自身に合った商品を選ぶことが可能です。
受給時期は原則60歳からとなっているので公的年金と足して受け取ることができます。
また、iDeCoで掛け金を積み立てる場合、会社員であれば年末調整時に書類を提出することで所得税の控除を受けられることがあります。
https://ichirandatabase.com/nenmatutyousei-sikumi-seido-rikaideyuukoukatuyou/
国民年金基金
国民年金基金は、個人事業主やフリーランスの方が厚生年金の代わりとして任意で加入することができる年金制度です。
積み立てる保険料は口数制で、受け取る金額と給付の方法を選択できます。
ただし、他の年金制度と同じく65歳以上からしか受給できません。
また、国民年金に経済的な理由などで加入できない方や免除を受けている方は国民年金基金に加入することはできません。
個人年金保険
個人年金保険は、保険会社が年金商品として扱っているもので、老後の資金源として積み立てることができます。
iDeCoが発足される前は個人年金保険を生命保険と共に加入し、積み立てる方が多かった制度です。
保険料を毎月、または一時金として年ごとに支払い、65歳の年金受給時などに合わせて受給できる制度です。
私的年金のメリット
- 積み立てている金額は全て所得控除になるので節税効果になる
- 私的年金を活用することで、将来の受給額を増やすことが可能になる
- iDeCoは専業主婦の方など扶養者も加入することができる
私的年金のデメリット
- 受給できる年齢制限と条件がある
- 運用は個人で行うので利益が出ない場合もある
給付される年金の種類

給付される年金の種類は公的年金の場合3種類あります。
給付タイミングは老齢に達した場合・障害状態になった場合・亡くなった場合に分かれますのでそれぞれを下記で解説します。
老齢年金
公的年金の国民年金・厚生年金に加入していた人に65歳から給付されます。
受給要件は、10年以上納付期間があれば受け取れます。
給付される年金の種類は以下です
| 国民年金 | 老齢基礎年金 | 20歳から60歳まで40年間保険料を納めると、満額の年780,900円程 |
|---|---|---|
| 厚生年金 | 老齢厚生年金 | 支払った金額に比例 |
障害年金
障害年金は怪我や病気などにより働けなくなってしまった場合に受給できる制度です。
また、障害の度合いや家族構成により受給金額は異なります。
なお、生まれつき障害を負っている場合や20歳未満に障害を負った場合は20歳から障害基礎年金が受給できます。
給付される年金の種類は以下です
| 国民年金 | 障害基礎年金 | 20歳から60歳まで40年間保険料を納めると、満額の年780,900円程 |
|---|---|---|
| 厚生年金 | 障害厚生年金 | 支払った金額に比例 |
遺族年金
遺族年金は公的年金の被保険者本人被保険者が亡くなってしまった場合に、被保険者の家族が受給できる年金制度です。
被保険者の配偶者は無条件で受給することができ、子の場合は条件が異なります。
遺族年金給付の対象となる子の条件
| 18歳に達した年度の3月31日を迎えていない子 |
| 障害状態にある20歳未満の子 |
私的年金はどれをやるべきか
結論から言うと、iDeCoが最もオススメな制度と言えます。
月々定額で積み立て、利益を見込める金融商品から運用を自身で行うことができるだけでなく、利益が出ても非課税措置が取られることなどもオススメな理由のひとつです。
また、積み立てた金額はすべて所得控除扱いにできるため節税効果も高いです。
まとめ

平均寿命は年々伸びていて人生100年時代と言われるようになりました。
人生が長くなる分、必要資金も増えます。
しかし少子高齢化により既存の公的年金に頼ることができないと言われていますので、厳しい意見ですが自分で老後資金を備える必要があります。
計画的に自分の資産を運用し、老齢時に経済的困窮とならないよう制度を上手に活用しましょう。