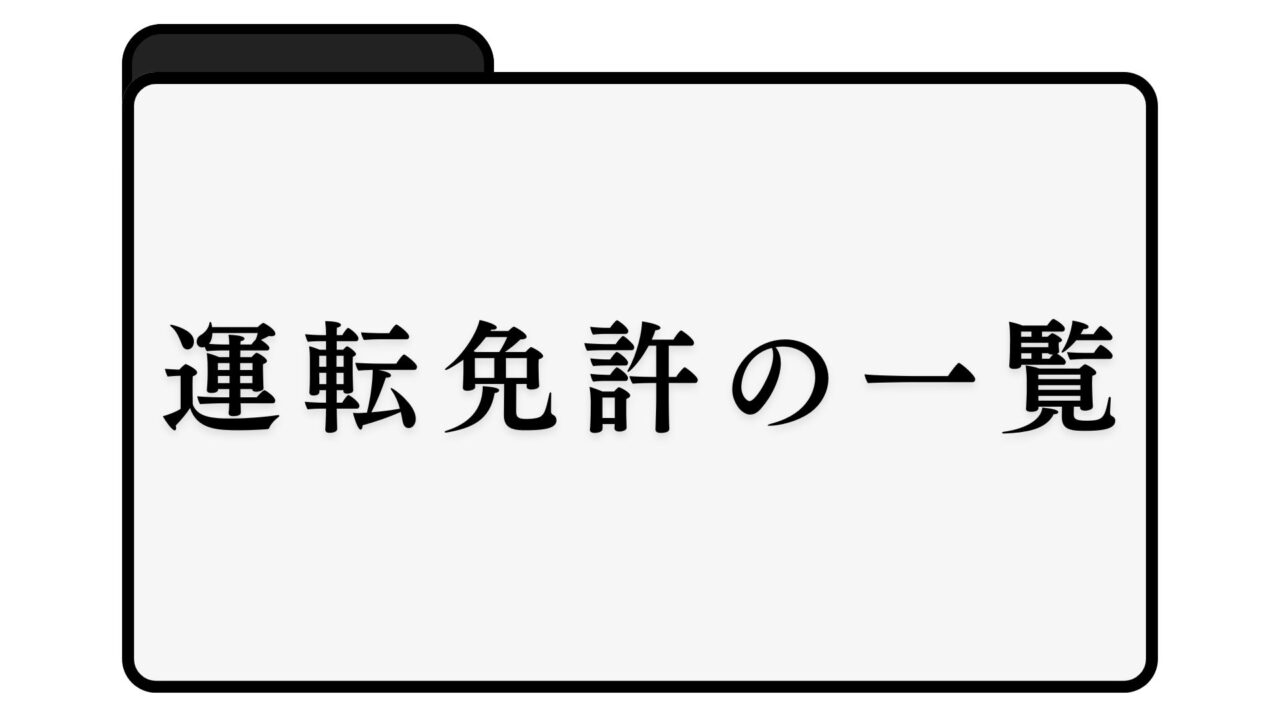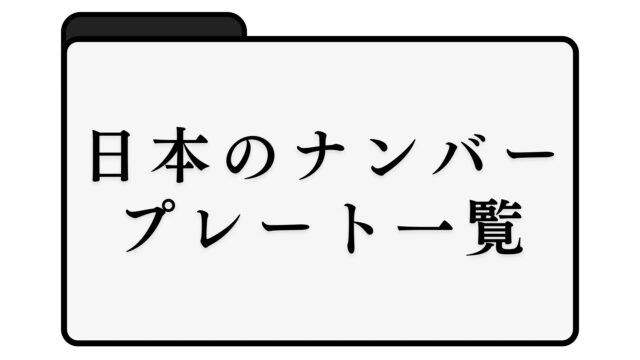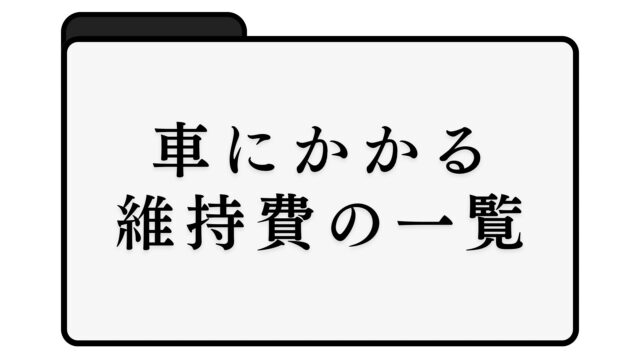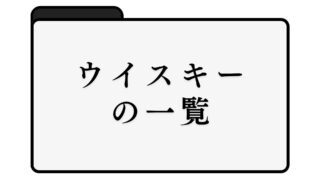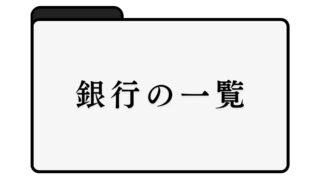今回は、日本で取得可能な運転免許について、種類、取得条件、運転できる車の範囲、取得難易度、費用、講習日数、カリキュラムなどを具体的にご説明します。
日本の運転免許は、大きく分けて「第一種運転免許」「第二種運転免許」「仮運転免許」の3つに分類されます。
1. 第一種運転免許
自動車や自動二輪車を運転するために必要な基本的な免許です。旅客運送(バスやタクシーでお客さんを乗せて運賃をもらうなど)の目的で運転することはできません。
1.1. 大型自動車免許 (大型免許)
運転できる車
車両総重量: 11トン以上
最大積載量: 6.5トン以上
乗車定員: 30人以上
大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車
取得条件
年齢: 21歳以上 (自衛官は19歳以上)
免許経歴: 普通免許、準中型免許、中型免許、大型特殊免許のいずれかを取得しており、その運転経歴が通算して3年以上あること。(自衛官は2年)
視力: 両眼で0.8以上、かつ、一眼でそれぞれ0.5以上であること。深視力検査で平均誤差2cm以内。
色彩識別能力: 赤・青・黄の3色が識別できること。
聴力: 10mの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること (補聴器により補われた聴力を含む)。
運動能力: 自動車等の安全な運転に必要な認知、判断及び操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがないこと。
取得難易度: 高い。車両が大きく、運転技術や安全確認のレベルが高いものが求められます。特に一発試験の合格率は低いです。
取得費用 (目安)
指定自動車教習所
中型免許所持: 約20万円~35万円
準中型免許(5t限定MT)所持: 約30万円~45万円
普通免許MT所持: 約35万円~50万円
一発試験: 受験料・試験車使用料・取得時講習料等で数万円程度。ただし、合格まで複数回かかることが多い。
講習日数 (目安)
指定自動車教習所 (通学):
中型免許所持: 技能14時限~、学科1時限~。最短7日~(合宿の場合)。通学で1ヶ月程度。
普通免許MT所持: 技能30時限~、学科1時限~。最短15日~(合宿の場合)。通学で1.5ヶ月~2ヶ月程度。
講習カリキュラム (指定自動車教習所の場合、所持免許により異なる)
学科教習: 大型自動車の構造と特性、点検、積載、危険予測など。
技能教習:
基本操作、車両感覚の習得
課題走行 (隘路、路端停車・発進、方向変換、縦列駐車、坂道発進など)
路上走行 (交通法規遵守、安全確認、危険予測)
応用走行 (状況に応じた運転)
1.2. 中型自動車免許 (中型免許)
運転できる車
車両総重量: 7.5トン以上11トン未満
最大積載量: 4.5トン以上6.5トン未満
乗車定員: 11人以上29人以下
中型自動車、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車
取得条件
年齢: 20歳以上 (自衛官は19歳以上)
免許経歴: 普通免許、準中型免許、大型特殊免許のいずれかを取得しており、その運転経歴が通算して2年以上あること。(自衛官は1年)
視力: 両眼で0.8以上、かつ、一眼でそれぞれ0.5以上であること。深視力検査で平均誤差2cm以内。
その他: 色彩識別能力、聴力、運動能力は大型免許と同様。
取得難易度: やや高い。普通車より大きく、運転感覚が異なります。
取得費用 (目安)
指定自動車教習所:
普通免許MT所持: 約18万円~30万円
準中型免許(5t限定MT)所持: 約15万円~25万円
一発試験: 数万円程度 (合格までの回数による)
講習日数 (目安)
指定自動車教習所 (通学):
普通免許MT所持: 技能15時限~、学科1時限~。最短8日~(合宿の場合)。通学で2週間~1ヶ月程度。
講習カリキュラム (指定自動車教習所の場合、所持免許により異なる)
学科教習: 中型自動車の構造と特性、点検、積載、危険予測など。
技能教習:
基本操作、車両感覚の習得
課題走行 (隘路、路端停車・発進、方向変換、縦列駐車、坂道発進など)
路上走行
限定免許:
中型自動車8トン限定免許
2007年6月1日以前に普通免許を取得した人は、この限定付き中型免許を保有しています。
運転できる車
車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満、乗車定員10人以下。
限定解除審査に合格することで、限定なしの中型免許を取得できます。
費用は約10万円~15万円、技能教習は5時限~です。
1.3. 準中型自動車免許 (準中型免許)
2017年3月12日に新設された免許区分です。
運転できる車
車両総重量: 3.5トン以上7.5トン未満
最大積載量: 2トン以上4.5トン未満
乗車定員: 10人以下
準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車
取得条件
年齢: 18歳以上
免許経歴: 不要 (初めて取得する免許としても可能)
視力: 両眼で0.8以上、かつ、一眼でそれぞれ0.5以上であること。深視力検査で平均誤差2cm以内。(※普通免許と同じ視力条件で取得できる限定準中型免許もあるが、教習所では深視力検査を求めることが多い)
その他: 色彩識別能力、聴力、運動能力は大型免許と同様。
取得難易度: 普通免許よりやや高い。車両が少し大きくなります。
取得費用 (目安)
指定自動車教習所 (免許なし、または原付免許所持): 約35万円~45万円
普通免許MT所持: 約15万円~20万円
講習日数 (目安)
指定自動車教習所 (免許なしの場合、通学): 技能41時限~、学科27時限~。最短17日~(合宿の場合)。通学で1.5ヶ月~2ヶ月程度。
講習カリキュラム (指定自動車教習所の場合)
学科教習: 普通免許の学科内容に加え、準中型自動車の特性や積載に関する内容。
技能教習: 普通免許の技能教習内容に加え、準中型車両での車両感覚、積載を考慮した運転など。
限定免許
準中型自動車5トン限定免許: 2007年6月2日から2017年3月11日までに普通免許を取得した人は、この限定付き準中型免許を保有しています。
運転できる車: 車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満、乗車定員10人以下。
限定解除審査に合格することで、限定なしの準中型免許を取得できます。費用は約7万円~10万円、技能教習は4時限~です。
1.4. 普通自動車免許 (普通免許)
最も一般的な免許です。
運転できる車
車両総重量: 3.5トン未満
最大積載量: 2トン未満
乗車定員: 10人以下
普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車
取得条件
年齢: 18歳以上
視力: 両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上であること。または、一眼の視力が0.3に満たない者若しくは一眼が見えない者については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること。
色彩識別能力: 赤・青・黄の3色が識別できること。
聴力: 10mの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること (補聴器により補われた聴力を含む)。
運動能力: 自動車等の安全な運転に必要な認知、判断及び操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがないこと。
取得難易度: 標準的。学科試験と技能試験があります。教習所に通えば比較的取得しやすいです。
取得費用 (目安)
指定自動車教習所 (AT限定): 約25万円~35万円
指定自動車教習所 (MT): 約27万円~37万円 (AT限定より1.5万~2万円程度高い)
一発試験: 数万円程度 (合格までの回数による)
講習日数 (目安)
指定自動車教習所 (通学):
AT限定: 技能31時限~、学科26時限~。最短13日~(合宿の場合)。通学で1ヶ月~3ヶ月程度。
MT: 技能34時限~、学科26時限~。最短15日~(合宿の場合)。通学で1ヶ月~3ヶ月程度。
講習カリキュラム (指定自動車教習所の場合)
学科教習 (第一段階・第二段階): 交通法規、安全運転の知識、応急救護処置など。
第一段階 (基本): 運転者の心得、信号、標識・標示、安全な速度と車間距離など (10時限)
応急救護処置 (3時限)
第二段階 (応用): 危険予測、高速道路での運転、悪条件下での運転、自動車の保守管理など (16時限)
技能教習 (第一段階・第二段階):
第一段階 (所内): 基本操作、発進・停止、S字・クランク、坂道発進、方向転換、縦列駐車など。
AT: 最低12時限
MT: 最低15時限
第二段階 (路上): 実際の道路での走行、自主経路設定、高速教習。
AT/MT共通: 最低19時限
限定免許
AT限定免許: オートマチック車のみ運転可能。MT車を運転するには限定解除審査が必要です (教習所で技能4時限~、費用約5~7万円)。
1.5. 大型特殊自動車免許 (大型特殊免許)
クレーン車、ショベルカー、フォークリフト、トラクター(農耕用)などの特殊な作業用自動車を公道で運転するための免許です。作業自体には別途資格が必要な場合があります。
運転できる車
カタピラ式や装輪式で特殊な構造を持ち、特殊な作業に使用する自動車 (ロードローラー、タイヤローラー、ショベルローダー、フォークリフト、ロータリー除雪車、農耕用トラクターなど)
小型特殊自動車、原動機付自転車
取得条件
年齢: 18歳以上
視力等: 普通免許と同じ。
取得難易度: やや易しい~標準的。車両の操作が独特です。
取得費用 (目安)
指定自動車教習所 (普通免許所持): 約8万円~15万円
講習日数 (目安)
指定自動車教習所 (普通免許所持、通学): 技能6時限~、学科なし (学科は普通免許等で免除)。最短3日~(合宿の場合)。通学で1週間程度。
講習カリキュラム (指定自動車教習所の場合)
技能教習: 大型特殊車両の基本操作、方向転換、走行など。
1.6. 大型自動二輪車免許 (大型二輪免許)
排気量400ccを超えるバイクを運転できます。
運転できる車
総排気量400ccを超える自動二輪車 (側車付きも含む)
普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車
取得条件
年齢: 18歳以上
視力等: 普通免許と同じ。
取得難易度: やや高い。車体が重くパワーがあるため、バランス感覚と確実な操作が求められます。
取得費用 (目安)
指定自動車教習所 (普通二輪MT免許所持): 約8万円~15万円
指定自動車教習所 (普通免許所持): 約15万円~25万円
指定自動車教習所 (免許なし): 約20万円~30万円
講習日数 (目安)
指定自動車教習所 (普通二輪MT免許所持、通学): 技能12時限~、学科なし。最短5日~(合宿の場合)。通学で1~2週間程度。
講習カリキュラム (指定自動車教習所の場合)
技能教習: バランス、引き起こし、取り回し、スラローム、一本橋、波状路、急制動、課題走行など。
限定免許
AT限定大型自動二輪車免許: ATの大型二輪のみ運転可能。
※以前は「小型限定」「中型限定」という区分が二輪免許にありましたが、現在は「小型限定普通自動二輪免許」と「普通自動二輪免許」になっています。大型二輪には排気量限定はありません。
1.7. 普通自動二輪車免許 (普通二輪免許)
排気量50cc超400cc以下のバイクを運転できます。
運転できる車
総排気量50ccを超え400cc以下の自動二輪車 (側車付きも含む)
小型特殊自動車、原動機付自転車
取得条件
年齢: 16歳以上
視力等: 普通免許と同じ。
取得難易度: 標準的。バランス感覚が必要です。
取得費用 (目安)
指定自動車教習所 (普通免許所持): 約8万円~18万円
指定自動車教習所 (免許なし): 約15万円~25万円
講習日数 (目安)
指定自動車教習所 (普通免許所持、通学、MT): 技能17時限~、学科1時限~。最短7日~(合宿の場合)。通学で2週間~1ヶ月程度。
指定自動車教習所 (免許なし、通学、MT): 技能19時限~、学科26時限~。最短9日~(合宿の場合)。通学で1ヶ月~2ヶ月程度。
講習カリキュラム (指定自動車教習所の場合)
学科教習: 普通免許と共通の部分が多い。
技能教習: 大型二輪と同様の課題を、普通二輪車両で行う。
限定免許
AT限定普通自動二輪車免許: ATの普通二輪のみ運転可能。
小型限定普通自動二輪車免許: 総排気量125cc以下の普通二輪のみ運転可能。AT限定もあります。
取得費用 (普通免許所持、AT小型限定): 約8万円~12万円
講習日数 (普通免許所持、AT小型限定): 技能8時限~、学科1時限~。最短3日~(合宿の場合)。
1.8. 小型特殊自動車免許 (小型特殊免許)
農耕用トラクター(小型)、コンバイン、フォークリフト(小型)など、一定のサイズ・最高速度以下の小型特殊自動車を公道で運転するための免許です。
運転できる車
長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下(安全キャブやフレーム付は2.0m以下)、最高速度15km/h以下の特殊自動車。
原動機付自転車 (学科試験に合格した場合)
取得条件
年齢: 16歳以上
視力: 両眼で0.5以上であること。または、一眼が見えない者については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.5以上であること。
その他: 色彩識別能力、聴力、運動能力は普通免許と同様。
取得難易度: 易しい。学科試験のみ、または簡単な実技講習で取得できる場合が多いです。
取得費用 (目安)
運転免許試験場で直接受験: 数千円程度 (受験料、交付手数料)。
教習所ではあまり単独のコースはありません。
講習日数 (目安)
学科試験のみなら1日。
講習カリキュラム
基本的に学科試験のみ。一部地域や特定の車両を運転する場合、実技講習が必要なこともあります。
※普通免許など上位の四輪免許を持っていれば運転可能です。
1.9. 原動機付自転車免許 (原付免許)
総排気量50cc以下のバイク(原付バイク)を運転できます。
運転できる車
総排気量50cc以下の原動機付自転車。
取得条件
年齢: 16歳以上
視力等: 小型特殊免許と同じ。
取得難易度: 易しい。学科試験と原付講習の受講で取得できます。
取得費用 (目安)
運転免許試験場: 約8,000円~10,000円 (受験料、講習手数料、交付手数料)。
講習日数 (目安)
1日 (学科試験合格後、原付講習を受講)。
講習カリキュラム
学科試験: 交通法規に関するマークシート方式の試験。
原付講習: 基本操作、安全運転に関する実技講習 (3時限)。
※普通免許など上位の免許を持っていれば運転可能です。
1.10. 牽引免許 (けん引免許)
車両総重量750kgを超えるトレーラーなどを牽引する場合に必要な免許です。牽引する車(トラクターヘッドなど)を運転するための免許(大型、中型、普通など)も別途必要です。
運転できる車
車両総重量が750kgを超える被牽引車を牽引する場合。
取得条件
年齢: 18歳以上
免許経歴: 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許のいずれかを所持していること。
視力等: 大型免許と同じ (深視力検査あり)。
取得難易度: やや高い。連結部分の操作や後退が特に難しいです。
取得費用 (目安)
指定自動車教習所 (普通免許MT所持): 約12万円~18万円
講習日数 (目安)
指定自動車教習所 (普通免許MT所持、通学): 技能12時限~、学科なし。最短5日~(合宿の場合)。通学で1~2週間程度。
講習カリキュラム (指定自動車教習所の場合)
技能教習: 連結・分離作業、方向転換 (特に後退)、車両感覚の習得。
限定免許
牽引小型トレーラー限定免許 (ライトトレーラー免許): 車両総重量750kg超2,000kg未満のトレーラー限定。
農耕車限定牽引免許: 農耕用作業車に限定。
2. 第二種運転免許
旅客自動車(バス、タクシーなど)を旅客運送の目的で運転する場合に必要な免許です。第一種免許の内容に加え、旅客輸送に関する知識や技能が求められます。
取得条件として、年齢21歳以上で、大型・中型・準中型・普通・大型特殊いずれかの免許経歴が通算3年以上(または他の二種免許を所持)が必要です。視力条件も第一種より厳しくなります (大型免許と同等、深視力必須)。
2.1. 大型自動車第二種免許 (大型二種免許)
運転できる車
乗車定員30人以上の旅客自動車 (路線バス、観光バスなど)。大型一種で運転できる車も運転可能。
取得難易度
最も高い部類。高度な運転技術に加え、旅客への配慮が求められます。
取得費用 (目安)
指定自動車教習所 (大型一種所持): 約35万円~50万円。
講習日数 (目安)
指定自動車教習所 (大型一種所持): 技能18時限~、学科19時限~。最短9日~(合宿の場合)。
講習カリキュラム
旅客輸送を想定した運転、応急救護、旅客対応など。
2.2. 中型自動車第二種免許 (中型二種免許)
運転できる車
乗車定員11人以上29人以下の旅客自動車 (マイクロバスなど)。中型一種で運転できる車も運転可能。
取得難易度
高い。
取得費用 (目安)
指定自動車教習所 (中型一種所持): 約25万円~40万円。
講習日数 (目安)
指定自動車教習所 (中型一種所持): 技能18時限~、学科19時限~。最短8日~(合宿の場合)。
限定免許: 中型自動車8トン限定第二種免許もあります。
2.3. 普通自動車第二種免許 (普通二種免許)
運転できる車
乗車定員10人以下の旅客自動車 (タクシー、ハイヤーなど)。普通一種で運転できる車も運転可能。
取得難易度
やや高い。特に地理試験がある地域も。
取得費用 (目安)
指定自動車教習所 (普通一種MT所持): 約20万円~35万円。
講習日数 (目安)
指定自動車教習所 (普通一種MT所持): 技能18時限~、学科19時限~。最短8日~(合宿の場合)。
限定免許: AT限定普通自動車第二種免許もあります。
2.4. 大型特殊自動車第二種免許 (大型特殊二種免許)
運転できる車
カタピラバスや雪上バスなど、大型特殊自動車で旅客運送を行う場合。
取得難易度
特殊。需要が少ないため教習所も限られます。
取得費用/日数
教習所により大きく異なる。
備考: 非常に稀な免許です。
2.5. 牽引第二種免許 (けん引二種免許)
運転できる車
トレーラーバスなど、牽引自動車で旅客運送を行う場合。
取得難易度
特殊。需要が少ないため教習所も限られます。
取得費用/日数
教習所により大きく異なる。
備考: 非常に稀な免許です。
3. 仮運転免許
第一種免許(大型、中型、準中型、普通)を取得するために、路上で運転練習をする際に必要な免許です。
種類: 大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許、普通仮免許
取得条件
年齢: 各免許の取得可能年齢に達していること (普通仮免許は18歳以上)。
視力等: 各免許の視力・色彩識別・聴力・運動能力の基準を満たしていること。
学科試験: 各免許の第一段階学科試験に合格すること。
技能試験 (修了検定): 教習所内のコースで基本操作・課題走行の試験に合格すること。
有効期間: 6ヶ月
運転できる範囲
練習のためであること。
その自動車を運転できる第一種免許を3年以上受けている者、または第二種免許を受けている者などが同乗し指導すること。
「仮免許練習中」の標識を車両の前後規定位置に表示すること。
高速道路、自動車専用道路、混雑している道路での練習は不可 (一部例外あり)。
取得費用: 教習所の料金に含まれている場合が多い。試験場で直接受ける場合は数千円。
講習日数: 教習所の第一段階修了まで (普通車ATで最短6日程度~)。
カリキュラム: 各免許の第一段階の学科教習・技能教習。
免許取得までの一般的な流れ (指定自動車教習所の場合)
入校: 適性検査 (視力、聴力、運動能力など)
第一段階
学科教習: 交通法規、運転マナーなど。
技能教習: 教習所内のコースで基本操作、課題走行。
効果測定 (学科の模擬テスト)
修了検定 (技能試験) → 合格で仮免許取得 (原付・小型特殊・二輪・牽引・二種の一部を除く)
第二段階
学科教習: 応急救護処置、危険予測、高速道路の運転など。
技能教習: 路上での運転、自主経路設定、高速教習 (必要な免許種別)。
効果測定 (学科の模擬テスト)
卒業検定 (技能試験) → 合格で卒業証明書発行
運転免許試験場:
適性検査 (視力など)
学科試験 (卒業証明書があれば技能試験は免除) → 合格
免許証交付
まとめ
費用や日数: 上記はあくまで目安です。
教習所、地域、所持免許、キャンペーン、個人の進捗状況などによって大きく変動します。
また、合宿免許は通学より短期間・安価な傾向があります。
一発試験: 運転免許試験場で直接技能試験を受ける方法です。
費用は安いですが、合格率が非常に低く、何度も受験する必要がある場合が多いです。
運転に自信があり、練習環境を確保できる方向けです。
教育訓練給付制度: 一部の免許取得コースは、厚生労働大臣が指定する教育訓練給付制度の対象となる場合があります。
こちらはハローワークでご確認ください。
免許制度や料金は変更されることがあります。
必ず最寄りの運転免許試験場や指定自動車教習所の公式サイトで最新情報をご確認ください。
この情報が、あなたの免許取得の参考になれば幸いです!